アメリカでホームレスとアートかハンバーガー (14) 涙を流したヘイロー
いかにもカリフォルニアという晴天だった。バーガープロジェクトも80人を超え、終盤に差し掛かっていた。ここまで来ると慣れ切って、刺激も何もなく、プロジェクトは完全にルーチンワークと化していた。
しょせんはサラリーマンの生活。平日は仕事で、週末は誰もがするようにだらだら過ごす。気が向いたら絵を描いて、そうこうするうち夕方になる。最寄りのマクドナルドに出かけて、その日の体調や気分でハンバーガーを1~3個調達する。
その日は2個、つまり2人のホームレスを見つければよかった。まあ、1時間もあれば終わるだろう。と、店を出て3分も経たないうちにホームレスを発見する。正直さっさと終わらせて酒でも飲みたかったからラッキーである。
タコベルというアメリカではメジャーなメキシコ料理のファーストフード店、その駐車場の脇に広がる芝生に黒人の男が寝転んでいた。
傍らには自転車の車輪を器用に組み合わせて作ったらしい荷車があり、そこにキャリーケース、マウンテンバイク、ほうき、空のウォーターサーバーのボトルが、まとめて放り投げたら偶然積み重なったという感じで積まれている。荷車からは牛につけるようなロープが伸びていて、どうやらそれを腰に巻いて引くらしい。
私は近づいて声をかけ、そばに自転車を停めた。一瞬怪しむような表情を見せたが、説明すると快諾してくれた。彼はよくラッパーが頭にかぶっているアレ(ドゥーラグというらしい)を頭につけていた。しかし黒縁のメガネをかけているせいか、マルコムXを思わせる知的な雰囲気もある。
アンケートを取り出し、記入してもらう。その様子を何枚か撮影する。ローアングルから撮ろうと芝生に膝をつくと、青々として冷たい芝生の感触が短パンでむき出しの膝頭に心地よく伝わる。記入し終わったアンケートを見ながらスペルを確認する。「H・A・L・O」彼はうなづく。
「ハロ、か」するとノーと首を振って「ヘェイロォウ」だと言う。「オーケー。ヘイローだな」それでも気にくわないらしく「ヘェェイィィロォォゥ」だと強調する。怒っているのではない。むしろやり取りを楽しんでいる感じで笑っている。それを真似て何回か繰り返し声に出すと、ようやく合格だと言わんばかりの態度で納得してくれた。
ハンバーガーをかじり、肩を組んで写真を撮る。ホームレスにしては珍しく、何の臭いもしない。無臭だ。そういえば、着ているTシャツも短パンも妙に小綺麗だ。むろん、ホームレスとて好き好んで不潔でいる人はいない。実際、彼らはよく、毎日シャワーを浴びることができないことが辛いと訴える。そんな中、彼はよほど身なりに気を使っているに違いない。
ハンバーガーをかじってもらい、私もかじる。肩を組んで写真を撮る。10分とかからず終わる。後片付けをしていると、どこから来たのかと聞いてくる。日本だと答えると大げさなリアクションをとり、日本人はいいやつだ、いつか日本に行ってみたいなどと、まんざらでもない言葉を並べる。
気をよくした私は、彼の横に並んで座り、少し話すことにした。どこの出身かと聞くと、物語を語り始めるようなもったいぶった口調で、どこって言ったらいいのかと、遠い目をしてつぶやいた。
全米中を、何回も引っ越した。ミズーリ、アラバマ、マサチューセッツ、ニューヨーク。数え切れない。お袋は、学校のスクールバスの運転手をやってた。お袋はおれが子供のころに離婚して、一人で育ててくれた。
なんで離婚したのかって? 話せば長くなるんだけど、ドラッグレースって知ってるか? そう、めちゃくちゃなスピードで爆走するアレさ。死ぬこともある危険なレースだ。親父はそのレーサーだった。お袋は危ないから辞めてくれって何度も頼んだんだ。子供がいるのに、死んでもらっちゃ困るだろ? だけど親父はやめないし、レースに金はつぎ込むしで、どうしようもないから離婚したってわけさ。
ヘイローは話の端々で、まるで慣れ親しんだ友達のように、「な?」とか「わかるだろ?」なんて言いながら私を肘でつついてきた。それはまったく子供みたいというか、不自然なくらいのはしゃぎようだった。
それが逆に、私の憐憫を誘った。べつに「私」と話すことに喜んでいるのではない。人と話すこと、いや、人そのものに飢えているのだ。しかしふと気がつく。彼が頭にかぶっているのはドゥーラグなんて洒落たものではなく、単なる黒のHanesのパンツであることに。
「まあ、お袋はもう死んでるし、親父は結局どこにいるかも知らない。まあ、とうの昔に死んでるだろうけどな。」
他に身内はいないのかと聞くと、妹がいるという。
「でも、妹も死んだんだ。」
シスターと言われても姉か妹かわからない。聞けば妹だと言う。ヘイローはまだ54歳だ。彼より若いなら死ぬには早い。
「事故でな。警察のパトカーに轢かれたんだ、こう、ビュンッ、てな」
ヘイローはそう、車がぶつかるさまを左の拳を右の手のひらで大きくはじいて見せた。私は悔やみの言葉をかけた。
「いいんだ。妹はまだ死んでない。」
真意をはかりかねて、私は聞いた。どういう意味だ? 葬式だってあったんだろう。
「葬式には行かなかった。おれは妹が死んだのを見てない。だから、死んでないと思ってる」
それを聞いて思ったのは、ホームレスでも感傷的なことを言うんだなという、ひどく筋違いな感想だった。適当な言葉が見つからず、ああ、そうだな、きっと生きてるよと言っておいたが、我ながら心がこもっていなかった。
だが彼はそれを喜んで、「サンキュー、ブロ(兄弟)」と言ってまた肘で小突いて笑うのだった。そして彼はまた何やら勢いよく話し始めたが、いかんせん彼の話は冗長で、正直なところ私は飽きてきていた。なにより私にはもう一つハンバーガーが残っている。暇ではないのだ。これからあと一人ホームレスを見つけなくてはならない。
彼の話をしばらく聞き流し、タイミングを見計らって私は、ところでと切り出した。
「誰か友達いたら紹介してくれない? ほら、もう一人ホームレスの人が必要なんだ」
彼はセリフを忘れた役者みたいに口をもごつかせて、しぼむように押し黙った。
「友達はいない」――何か恥でも告白するように、彼は言った。それからもう一度、「友達なんかいない」と、開き直ったように笑った。つられて私も笑い、いや、でも一人くらいはと言いかけて、口をつぐんだ。
彼は泣いていた。黒縁めがねの間から、透明な涙が黒い頬をつたった。私はうろたえた。馬鹿でもわかる。大の大人が会ったばかりの他人の前で泣くことがどれだけ尋常ではないか。私は彼の涙を見て、初めてその孤独の深さに気がついたのだった。
私にとってホームレスは、もはや作品のモチーフでしかなくなっていた。鑑賞者は作品に入り込むのが常だが、逆に芸術家は作品を突き放す。だってそうだろう。たとえ感動的な映画でも、撮影中に監督も一緒になって泣いていたら世話はない。そんなのは間違いなく三流だ。
だから私はたとえ人間でも、パンやリンゴのような無機的な静物と同じように扱う。それがにわかに血を通わせ息づいて、ああだこうだとものを言い始めたのだから、衝撃を感じずにはいられなかった。
私は何も言えなかった。彼はその横で静かに泣いていた。なんとも言えず居心地が悪かった。誰でも一度や二度は、泣いている人の横でその悲しみに付き合ったことがあるだろう。あの、ただ時間が過ぎるのを待っている感じ。いつまで泣くんだろう。どうすればいいのか、どうすべきなのか。
でも、頭の片隅はひどく冷静で、この後あれをしようとか、これを食べようとか呑気に考えている。ちらと腕時計を見やる。5時57分。日が暮れるにはまだ早い。罰は当たらない。もう少しだけ付き合うかと、実利的な判断をする。
5分、10分。嗚咽こそ漏らさないが、時折彼は鼻をすすった。感情を押し殺しているのがいやでも伝わってくる。とても還暦の遠くないおっさんのそれではなく、少年のようなけなげさがあった。
私は心ある人間として、彼に共感して、同情しようと試みた。しかしパンツをかぶって泣いている姿はいかにも間抜けで、馬鹿馬鹿しくて、私の感傷を端から削ぎ落としてしまうのだった。
夕暮れの涼しい風が吹き始める。目の前の幹線道路を、無数の車が流れる。帰宅ラッシュの時間で、途切れることがない。ファーストフードの駐車場と、歩道の間に設けられた芝生。そこに私と彼は膝を抱えて並んで座っている。あまりにも人目につく場所でありながら、気を止める者はない。
いつか少年だった日に、こんな風景を見た気がする。あるいは私と彼がティーンエイジャーだったら、これはもう立派な青春の1ページになったろう。ちょうどトムソーヤとハックルベリーのような。トムは浮浪者のような暮らしをしているハックにあこがれたが、ヘイロー、私は君にあこがれることができない。
そうだ――急にヘイローは立ち上がった。ボールペンを返さなきゃな。そう言って彼は鼻をすすった。私が貸していた青のボールペンを差し出す。
しかしちょっと待てよと引っ込めて、彼は荷車に近づいた。積み荷からスプレー洗剤を引っぱり出す。それをボールペンに吹きかけ、くしゃくしゃのペーパータオルで拭いた。
「ほら、きれいになった」
彼はボールペンを差し出して、よく泣いたあとに見る、唇が引きつったような笑みを浮かべた。
「汚いから」
ありがとうと普通に受け取ったものの、私は喉元に何か涙っぽいものを込み上げてくるのを感じた。
彼の気遣いに感動したとかいうのではない。言うなれば予言者か何かに私という人間を想像を絶する精度で言い当てられ、どう受け止めていいかわからずパニックに陥ってしまったような。
実際、私はいつも家に帰ればホームレスが触れたものにはすべて除菌スプレーをかけて洗浄するのが常だった。しかし当の本人にそのように振る舞われると、私はどうしていいかわからなかった。
そろそろ行くよ――私は立ち上がった。彼はまたなと言った。私もまたなと返した。子供でもあるまいに、それが嘘であることが苦しかった。
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本シリーズは商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。アメリカでホームレスとアートかハンバーガー 全30回(予定)- (1) 銃撃されたラド
- (2) アメリカの普通
- (3) DNAの価値
- (4) ホームありの母親とホームレスの娘
- (5) 見えない境界線
- (6) 働くホームレス
- (7) 働かないホームレス
- (8) 古き良きアメリカンドリームの現実
- (9) 単身ロサンゼルスに移住して
- (10) 奴隷ビザの分際
- (11) アメリカの現実をアートに
- (12) 古今東西、臭いものには蓋
- (13) 蓋の蓋の蓋
- (14) 涙を流したヘイロー
- (15) ホームレスのリアル
- (16) 55万2,830人のホームレス
- (17) 恥か罪か運命か
- (18) 芸術という刀を振りかざす

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。
- 前の記事
- 2025/03/22 更新 個展「Bento」DE BOUWPUT(アムステルダム) 2025/2/4-2/9
- 次の記事
- 2025/01/13 更新 アメリカでホームレスとアートかハンバーガー (15) ホームレスのリアル
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。







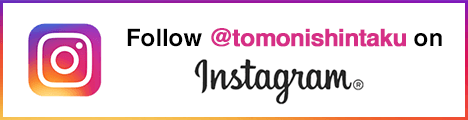

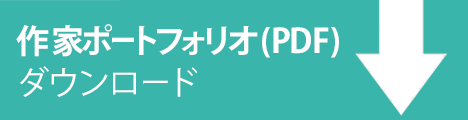

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。
わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!