アメリカでホームレスとアートかハンバーガー (12) 古今東西、臭いものには蓋
彼らに家はないが、不思議といつも決まった場所にいる。一切のしがらみ、会社も家族も家も車もない彼らはどこに行っても構わないはずだが、どうして、彼も彼女も、今日もまたそこにいる。いくら小さくても、ひどいあばら家でも、とにかく人間には家がなければならないらしい。
しばしばホームレスはバス停に住み着いている。アメリカのバス停と言っても、日本のものと大差ない。ベンチがあって、その上に簡素なひさしがついているだけである。しかし改めて眺めてみると、究極、家の原型とはこういうものかもしれないと思う。
通勤の中途に、エクソダスという病院がある。これはモーセが海を割る有名なくだりが入っている旧約聖書の「出エジプト記」という章の英語名である。エジプト人に迫害されていたヘブライ人を、モーセが先導しエジプトから脱出させたことからこう呼ばれる。
その「エクソダス前」バス停に、5、6人のホームレスが住んでいる、というか占拠している。最初見た時は、いまだ苦難を脱出できないからエクソダス「前」なのかと苦笑したものだ。
そのバス停は通院患者の休憩所を兼ねているらしく、10畳ほどはある。ちゃんと屋根もついている。壁もドアもなく吹きさらしだが、複数ベンチが設えられている。
そこでホームレスは朝から酒を呑んだり、雑談していたり、ただ座っていたりする。見通しのいい6車線道路の傍らにあって、一応バスも停まる。しかし本来の乗客はその「ホームレスの家」を避けて、10メートルかそこらの距離をおいて待っている。
その光景を、道路をはさんで遠くのぞむと、よそ行きのすました顔をしている一般人と、もはやプライベート空間としてくつろいでいるホームレスとで、悲劇だか喜劇だかの映画のセットのようにも見える。
バスの乗客がいないことは多々あったが、ホームレスがいないことは一度もなかった。いつ通っても誰かいる。固定のメンバーに加えて、入れ代わり立ち代わり様々なホームレスが集まる。それで私は、会社帰りにマクドナルドでハンバーガーを調達し、ほとんど毎日立ち寄るようになった。
世界広しと言えども、会社帰りにホームレスとハンバーガーをかじり合っている奴など、今までもこの先もいないだろう。そう思うと誇らしかった。
アーティストとは、誰もやっていないことに無上の喜びを感じる生き物なのだ。一日8時間、会社での苦役を終えれば即、自己実現の場が待っている。期待外れ以外の何ものでもないアメリカでの生活がにわかに色づき、今ここにいる確かな意味を感じた。
最初の頃こそホームレスらの反応はいかにも私を怪しんでいたが、ほどなく人が人を呼び、じきに向こうから気安く声をかけてくるようになった。
マクドナルドの店員にも顔を覚えられた。私が入店するが早いか「クォーターパウンダー?」と聞いてくる。
レシートも作品制作の一環として記録するため、余計なものは買わないから尚更だった。私は「イエス、プリーズ」と答えるだけでよかった。出来上がるまでの5分前後の間に、カメラをチェックし、アンケート用紙に「May 25」などと当日の日付を書き入れる。ハンバーガーを受け取ると、その紙袋の口元を自転車のハンドルに巻きつけて握り、いそいそとエクソダス前に向かう。
ホームレスに感じていた忌避感は、場数を踏むほどに薄らいでいった。抵抗どころか警戒心も忘れ、あるいは本当に好感を持って、バーガーチャレンジが終わったあとも腰を下ろして話をするようになった。何度も繰り返して接触すると好感を持ってしまう、ザイオンス効果(単純接触効果)もあったろう。
しかしなにより、私の個人的な生活環境や心理状況が影響を及ぼしていたことを告白しなければならない。
渡米後数ヶ月経っても、私には友達がいなかった。べつに交友関係に消極的だったわけではない。シンガポールで過ごした時と同じように、外国の友人を作るんだと意気込んで、男女問わずアプローチもした。しかし、シンガポールではうまくいったものが、アメリカではどうして芳しくなかった。
知り合いらしい知り合いもできない。深い考えもなく決めた家は、シェアハウスというかホームステイにも近かった。フィリピン系一家の戸建ての一部屋を間借りしていたのだが、どうかすれば居候と大差ない。
「居候三杯目にはそっと出し」とはよく言ったもので、金を払っていても肩身の狭さを禁じ得なかった。老夫婦と出戻りの娘、そして時に彼女の中学生にもならない子供が数人やって来る。結構な頻度で前夫も一緒にやって来て、時にはみんな揃って泊まっていくことも珍しくなかった。
断っておくが、彼らは決して悪い人たちではない。むしろとても気さくないい人たちだと思う。しかし大家と借り主という関係上、心から打ち解けることは望むべくもなかった。
心理的な壁に反して、一階にあるダイニングからは、毎日三度の食事のたびにいい匂いと彼らの笑い声が、2階にある私の部屋まで濃厚に、四六時中お構いなしに流れてくる。
仕事帰りに日系のスーパーでノリ弁なんかを買って帰り、缶ビール片手にもぐついていると、階下からパスタだろうかガーリックの匂いが漂ってくる。そして笑い声まで聞こえてくると、私は言いようのない苛立ちと寂しさを感じて耳を塞ぎたくなるのだった。
あるいは自慰行為の果てる頃にそのような匂いと声を聞くと、私は私の存在意義と価値をすっかり信じられなくなって、いっそ軽蔑して何もかもが嫌になってしまったことも一度や二度ではない。
孤独への耐性がないわけではなかった。むしろ孤独を愛する方だと言っていい。しかし、私が感じていたのは孤独というよりも疎外というべきものだった。
人は孤独でもけっこう平気で生きられるものだ。しかし疎外感を抱えて生きるのはほとんど不可能である。
たとえば孤独な人々が一年でもっとも堪えるのは、年末年始だと言われる。親類縁者が寄り集まり、嫌でも浮き足立った空気がみなぎるその時分、寄る辺ない彼らが感じるのは孤独ではない。世界中につまはじきされているような疎外感である。
私は、SNS上でこそ、あくまで精力的に作品制作に邁進しているように振る舞ってはいたが、狂おしいやりきれなさが積もり積もっていることは明らかだった。
それでホームレスらに、おざなりではなく心からの親近感を覚えるようになっていった。ほとんどのホームレスは、とても優しい。私のつたない英語でも、彼らは真剣に聞いてくれるし、彼らもまたざっくばらんに心を開いて話してくれる。それは私にとって、俗っぽい言葉で言えば癒やしに他ならなかったし、心の支えと言っても過言ではなかった。
エクソダス前に住んでいたメキシコ系の男女のカップルは、特に私の気に入りだった。男性の方はルイといって、痩せ型で筋肉質、どこかボクサーのような風貌。対照的に、パートナーのヘルミラはふっくらとして母親のような雰囲気である。
ホームレスになってカップルも何もないだろうという気もするが、いるところにはいる。歴史を紐解けば奴隷でさえ惹かれ合って結婚し、子供さえもうけたことを思えば、人間、一緒になるというのは理屈ではなく本能の領域なのかもしれない。
二人とも気のいい性格で、会えばいつでも笑顔で応じてくれる。立ち寄らない日でも、自転車で通り過ぎる際に手を振れば、ふたりともまるで長年の友人のような気安さで手を振り返してくれる。そうして笑顔を作った時に、自分がその日初めて笑ったことに気がついたりする。
一度、缶ビールを買って行ったことがある。ルイは喜んで受け取り口をつけたが、ヘルミラはアルコールは飲まないらしかった。
ルイは手を油で真っ黒にして、自転車の修理だか改造だか、車輪が外されたフレームを、ガキン、ガキン、ガキンとハンマーで叩いていた。それをヘルミラは、近くのベンチに座って見るともなしに見ていた。私はその中ほどに立って、ビール片手にその様子を眺めた。
しゃにむにハンマーを振り上げるルイを指差して、何をしているのかとヘルミラに尋ねた。彼女は、さあねといった風に肩をすくめて笑った。ルイはたまに手をとめて、私のあげたビールを口に含んだ。
ガキン、ガキン、ガキン――。この二人にわずかばかりの金と、せめてワンルームの部屋でもあれば、彼らはもう、まったく世にも美しいカップルになるに違いなかった。
もちろん、金も家もなくたって、彼らを美しいと形容することは可能だ。恋愛というものはしばしば金銭や地位を度外視した純粋性を求める。
しかし、現実問題、ひとつの極北であるホームレスにまで落ちたとすれば、我々がふだん愛と呼んで疑わない程度の愛など、たちまち跡形もなく吹き飛んでしまうのではないだろうか。
不意にルイが手を止めて、彼の家であるテントに潜り込む。口の開いた、くしゃくしゃになったミックスナッツの袋を差し出す。ホームレスから食べ物をもらうのは滑稽な気がしたが、私は一粒だけもらった。
そのあと彼は、それをざーと口に流し込んで、ぼりぼり言わせながらビールをあおった。そしてまた彼は、何をどうしたいのか、ガキン、ガキン、ガキンと作業を続けた。
それは信じられないくらい平和で、罪のない時間だった。とはいえ、私が彼らの中になにがしかの美や善を見出すのは、ある種の現代病かもしれない。都会に暮らす人は、往々にして田舎やそこに住む人々のことを美しく純朴だと勝手に思い込みたがるのと同じである。
ただ、どこの世界にも、素晴らしい人がいて、どうしようもない人がいて、そして当たり障りのない人が大勢を占める、というのは変わらないと思う。
ジョンという大男はいつも酒を飲んでいる。西洋絵画に出てくるような丸っこい赤ら顔で、あおり方も酔い方も堂に入っている。
最初に会った日もやはり缶ビールのロング缶を片手に酔っていた。私は面倒な輩は避けようと思い他を当たろうとしたが、顔見知りのホームレスがこいつは10バックス(10ドル)くれるよと吹き込んだ。
彼は身を乗り出してきて、私は仕方なく彼に説明する羽目になった。快諾してくれたはいいが、問題はそこからだった。ハンバーガーを全部食べようとするし、写真を取る時には肩を組むどころかハグまでされて、そのままだんだん力が強くなり、しまいには絞め殺されるかと思った。
また別の日には、ヘレンという初老の女性が、私に興味を持って話しかけてきた。彼女はとりとめもなく一方的にしゃべり続けた。私はしばらく黙って聞き続けたのち、ようやくでバーガーチャレンジの説明を切り出した。難なく引き受けてくれたが、肩を組む段になると、首に手を回しキスしようとしてきたのには参った。
それでも私はエクソダス前が好きだった。会社にいる時みたいに常識人を演じなくてもいいし、すべて本音で接して構わない。気取らず、気負わず、素直に笑える場所は他になかった。
よくこんなことを夢想した。彼らが一般人で、私は彼らとふつうの友達だったら、どれだけよかったろうと。SNSでやり取りをして、彼らと日常の出来事や考えを共有したり、ごはんを食べに行ったり、飲み会を開いたり、あるいはどこかに遊びに行ったりする。
自分の存在を一般人にカテゴライズして、彼らを一般から外れた存在と捉えるのは、私のおごり、傲慢で、それこそ倫理にもとるかもしれない。
しかし、私には家があって、彼らには家がない。家の有無。それだけのことなのに、その壁は、とてつもなく厚く、恐ろしく高い。
きっとマザー・テレサなんかなら、同じ人間としてこだわらなかったろう。しかし私は慈善家はおろか、善人にさえなれないから、彼らとはどこまで行っても、一般人とホームレスという壁越しにしか付き合えないし、付き合わない。
それはとても悲しいことだと思う反面、一般人としての私は、そんなことは自明で、当たり前だろうとも思う。親や友人にどう思うか聞いてみようか。否、聞いてみるまでもない。
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本シリーズは商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。アメリカでホームレスとアートかハンバーガー 全30回(予定)- (1) 銃撃されたラド
- (2) アメリカの普通
- (3) DNAの価値
- (4) ホームありの母親とホームレスの娘
- (5) 見えない境界線
- (6) 働くホームレス
- (7) 働かないホームレス
- (8) 古き良きアメリカンドリームの現実
- (9) 単身ロサンゼルスに移住して
- (10) 奴隷ビザの分際
- (11) アメリカの現実をアートに
- (12) 古今東西、臭いものには蓋
- (13) 蓋の蓋の蓋
- (14) 涙を流したヘイロー
- (15) ホームレスのリアル
- (16) 55万2,830人のホームレス
- (17) 恥か罪か運命か
- (18) 芸術という刀を振りかざす

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。
- 前の記事
- 2025/04/06 更新 いろんな意味でサーカス
- 次の記事
- 2024/11/18 更新 アメリカでホームレスとアートかハンバーガー (13) 蓋の蓋の蓋
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。







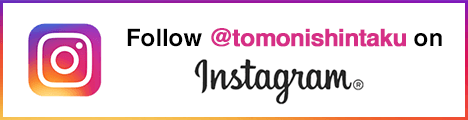

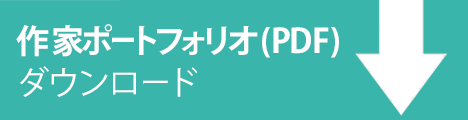

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。
わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!