図解 カメラの歴史 ダゲールからデジカメの登場まで (神立尚紀/ブルーバックス)
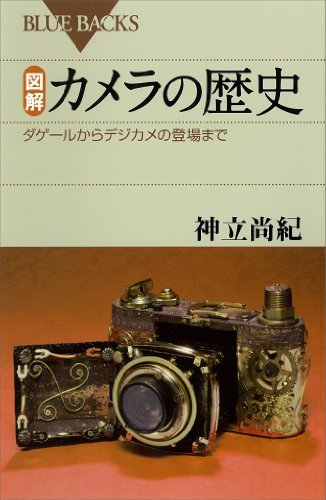
購入価格:991円
評価:
この記事は約1分25秒で読めます
「すぐ役に立つことは、すぐ役に立たなくなる」とは、よく言ったものである。慶應義塾大学の塾長であった小泉信三の言葉だが、私の信条である。
カメラとは何か
簡単に今すぐプロみたいにうまく撮れるという類のハウツー本はごまんとあるが、カメラを始めるすべての人が最初の段階で読むべき本だと思う。いま自分が持っているカメラなるものが、いつ始まり、何がどうなって現代のような形になったのかという歴史的経緯が概観できる。すると、自分の持っているカメラが、先達の血と汗と涙の結晶というべき、感動的なモノにも思えてくる。
日本のカメラが花開く
「ニコン神話」のはじまりという章にある話には感銘を受けた。1950年、日本製のレンズがまだ評価されていない頃の話だ。ある夕暮れ時、日本の新製品のレンズだと言って、「ライフ」誌の写真家デビッド・ダグラス・ダンカン氏を数枚撮影した。
「日本製のゾナーレンズです」と説明すると、彼は小馬鹿にするように「ほほう、日本製のキャデラックはどこにあるだい」と笑った。後日、彼のもとにその時に取った写真が届けられた。その写真に彼は驚いた。夕暮れ時で、光量不足だと思っていたのにも関わらず、あまりにもクリアに写っていたからだ。
その時使われたレンズはニッコール85ミリF2だったが、彼は反駁する。「あれは黄昏どき、灯りをつけない状態だった。あんな暗がりで85ミリF2はあり得ないよ。(中略)50ミリF1.5だと信じている」と。
知らなければわからない話
このくだりは、カメラの絞りや露出を理解し始めた私にはなるほどと、深く感じ入るものがあった。私はひとり、声を出して唸っていた。絞りや露出を知らなければ、このやり取りの機微も理解できないに違いなく、知っているからこそおもしろいと思えたのである。
とまれ、本書には大学の授業などで使われてもおかしくないレベルの知識が満載されている。写真を志すすべての人におすすめしたい。
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
名著12篇に学ぶ中国古典の人間学
2012/12/03 エッセイ migrated-from-shintaku.co
読み始めてから二か月以上くらい経っているような気がする。ほんとにちょっとずつ、ご ...
新型肺炎 感染爆発と中国の真実 中国五千年の疫病史が物語るパンデミック
2020/03/31 エッセイ migrated-from-shintaku.co
何故いつも中国から病が発生するのかと思っていたのが腑に落ちた。ヘイト的な偏見を排 ...










