NFT解説本【補足動画付き】なぜ、デジタルアートが75億円で売れるのか? (足立明穂/Kindle出版(KDP))
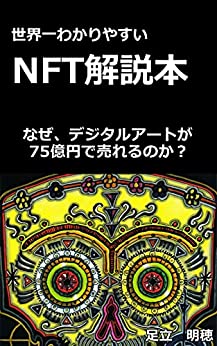
購入価格: Kindle Unlimited(0円)
評価:
この記事は約1分23秒で読めます
最近やたらとよく聞くようになったNFTだが、まったく理解していなかったので、素直にいちから勉強することにした。
本書はそんな初心者にも優し過ぎるくらいに優しい。NFTの仕組みを知らなければNFT作品もクソもないので、これで遠くない将来、NFTを絡めて云々というアイデアが思いつけそうな気がする。
NFTは、何を可能にしたのでしょうか?いろいろな見方があるのですが、さまざまな権利を移動できるようにしたのではないでしょうか。絵画のオリジナルを所有する権利、コンサートで前から3列目の右から3番目に座る権利、アイドルと握手する権利……。これらの権利を、所有者から譲り受ける、つまり、権利が移動していく仕組みが出来上がったのです。
『実際に取引されるのはデジタル署名を意味する「非代替性トークン」(NFT)で、暗号資産(仮想通貨)を支える基盤技術のブロックチェーンでオンラインデータの所有者を証明する。』 (中略) NFTはコピーさせない技術ではありません。コピーがあっても、オリジナルがどれなのかを証明できるという技術です。リアルのアート作品でも、コピーは大量にされていて、美術の本に印刷されていたり、Tシャツや絵葉書になっていたりするでしょう。リアルは、明らかに品質(素材)が異なるのですが、デジタルの場合は、全く劣化しないので、オリジナルであることの証明が難しかったのです。それが、NFTを使うことで可能になったのですね。
アート作品などが、2次売買で売れた時もロイヤリティがアーティストに支払われるのを、追求権といいます。EU加盟国などでは、この追求権が定められていて、オークションなどで2次売買されても、アーティストに収益が発生します。残念ながら、日本では、追求権は採用されていないので、そのような仕組みがありません。
- 前の記事
- 話し方の知恵―こんなときどう話す
- 次の記事
- プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
お金の話に強くなる! 為替のしくみ ~為替レートが動く理由と相場のカラクリがわかる!
2023/03/06 エッセイ
金が欲しいという人はいくらでもいるだろうが、しかし、金のことをちゃんと知っている ...
航空事故―その証跡に語らせる
2015/08/16 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co
民俗学者の柳田国男がこんなほんと書いてんのかー、と間違えて購入した本。こちらは柳 ...










