FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 (ハンス・ロスリング (著), オーラ・ロスリング (著), アンナ・ロスリング・ロンランド (著), 上杉 周作 (翻訳), 関 美和 (翻訳)/日経BP)
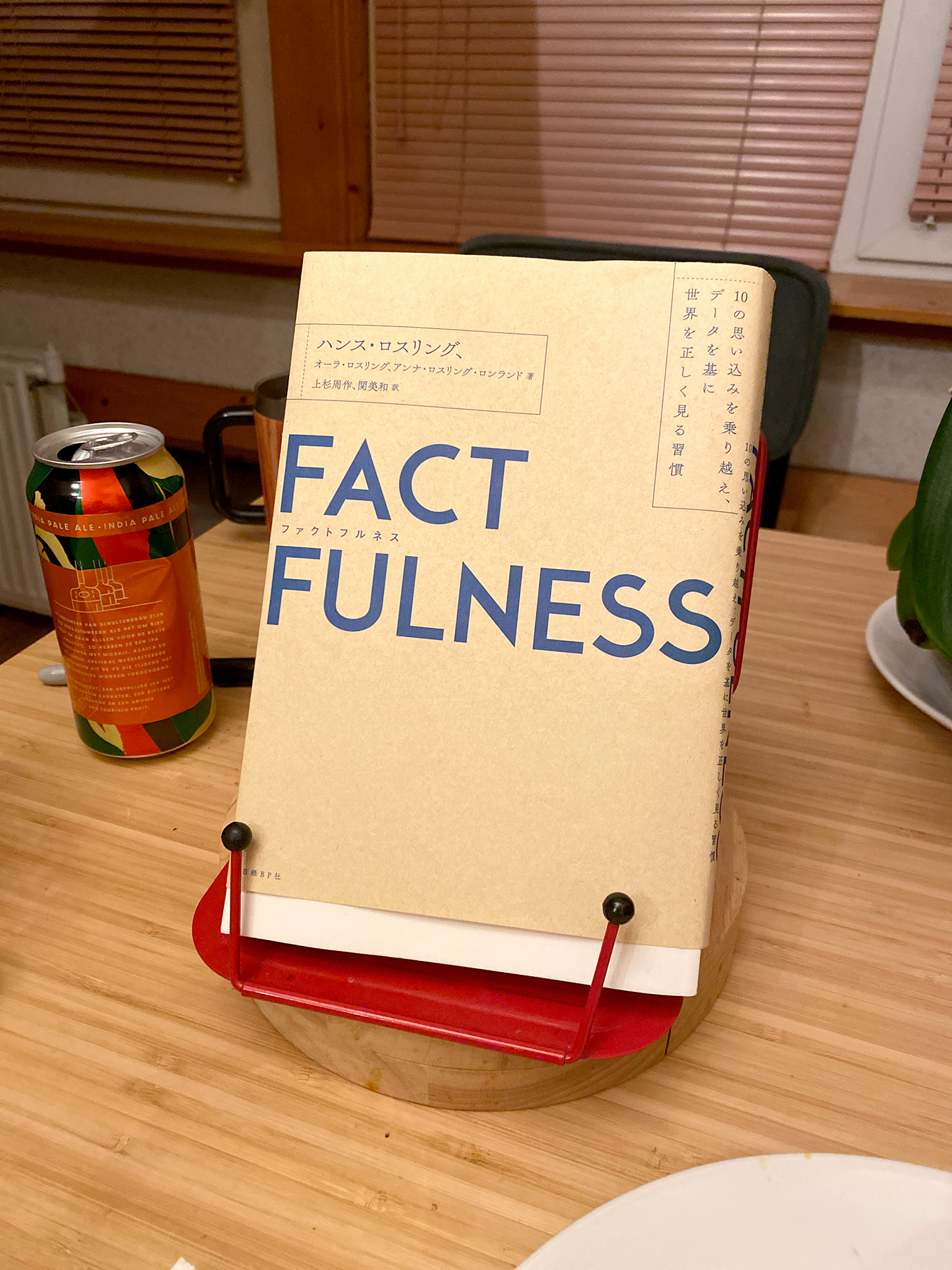
購入価格: Kindle Unlimited(0円)
評価:
この記事は約2分37秒で読めます
間違いなく今年一番読む価値があったと思える一冊。
私はネガティブ気質のせいもあって、世界はクソでどうしようもないと常々思っていたが、いやいや、しっかり向上もすれば改善もしているのだということを認めざるをえない。
世界を悲観的にとらえるのは勝手だが、事実を捻じ曲げてまで悲観するのは流石に問題があろう。しかし現実に、多くの人が世界をネガティブにとらえたがり、正しく見ることができていない。
世界は少しずつ、着実によくなっている。そして、これからもっとよい時代がくる。
素直にそのような視点を得られたことは、なにものにも代え難い価値がある。
ネガティブ本能が刺激される理由はもうひとつある。そもそも、「世界はどんどん悪くなっている」という人は、どういう考え方をしているのだろう。わたしが思うに、そういう人たちは実はあまり深く考えておらず、なんとなく感じているだけだ。
1800年まで、女性ひとりあたりの子供の数は平均6人だった。本来なら、人口は増えていくはずだ。しかし、そうはならなかった。古代の遺跡には、子供の骨が多く埋まっていると話したことを思い出してほしい。6人の子供のうち平均4人は若くして亡くなってしまい、大人になれるのは2人だけだった。だから、人口が増えなかった。昔の人は、自然と調和しながら生きていたのではない。自然と調和しながら死んでいったのだ。世界は残酷だった。
「こっちではベトナム戦争じゃなくて、対米抗戦って呼ぶんですよ」とニエムさん。たしかに言われてみれば、あの戦争を現地の人が「ベトナム戦争」と呼ぶわけがない。
近代医学が発達する前、最悪の皮膚病は梅毒だった。痛がゆい水ぶくれから始まって、ただれが骨まで届き、骨が見えてしまう。気味の悪い見た目と耐えられないほどの痛みを引き起こすこの病気は、国によって呼び名が違っていた。ロシアではポーランド病と呼ばれ、ポーランドではドイツ病と呼ばれた。ドイツではフランス病。フランスではイタリア病。イタリアはやり返したかったのか、フランス病と呼んでいた。
- 前の記事
- 奇跡の脳―脳科学者の脳が壊れたとき
- 次の記事
- 私の財産告白
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。










