喧嘩両成敗の誕生 (清水克行 /講談社)
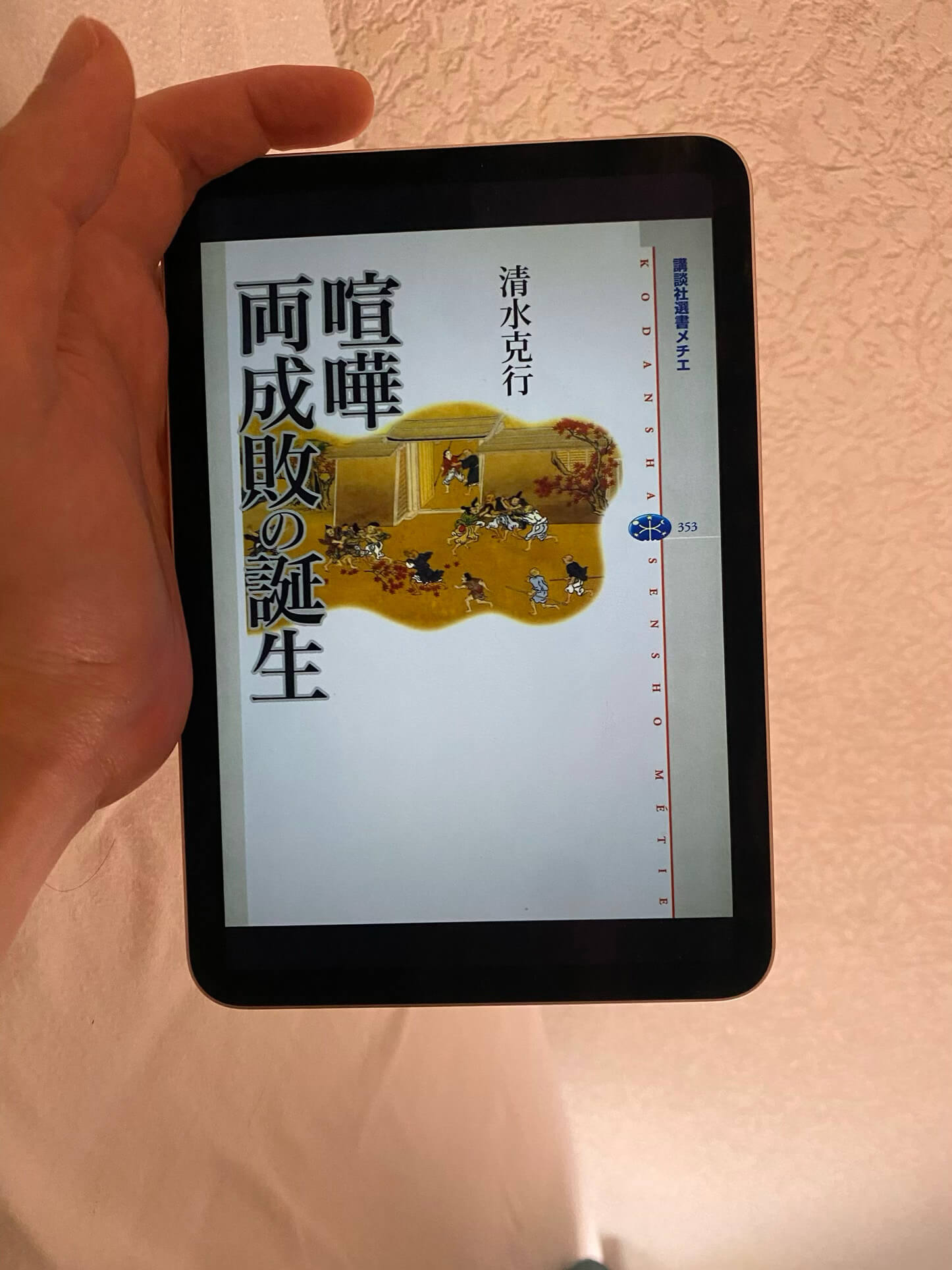
購入価格:880円
評価:
この記事は約2分37秒で読めます
ふつうに考えれば、喧嘩両成敗などというのは判断することを放棄した、コインの裏表で決める、占いにも近いものである。
しかしいまだにこの考えが通用するのは、閉じられたコミュニティの中で、波風を立たせないための知恵だと考えれば納得がいく。どんなに正しい裁きでも、どちらかの考えが認められれば、それは必ずしこりを残すものだ。
ゆえに、どちらも良く、どちらも悪いという、なんとも奇妙な判断で一件落着とする。しかし、この心性は、間違いなく現代日本人にも連綿と続いている。
江戸時代以降、切腹というものが武士身分にだけ許された自害方法で、それ自体が身分特権であったということはよく知られている。これに対し、少なくとも室町時代については、僧侶や女性も切腹をしているので、そうした意識はまだ形成されてはいなかったようだ。
いまの日本においても「死をもって潔白を訴える」「抗議の自殺」「憤死」といった言動が子供の世界のイジメから芸能人や学者の醜聞、政治家の汚職事件にいたるまで価値を持ち続けているという深刻な現実があることを忘れてはならない。その一方で、欧米社会ではそうした傾向は見られず、むしろ逆に係争中に一方がみずから命を絶つようなことがあれば、それは敗北を認めたのと同様にみなされるとも聞く。そして、彼我の相違から、日本人はある主張の是非を判断するとき、その主張が論理的に正しいかよりも、主張者がその主張にどれだけの思いをこめているかを基準にする傾向がある、と指摘するむきもある。
なかでも滑稽なのは「押蒔き」や「押植え」といった行為である。これは、係争中の土地の支配を主張するために、その土地に勝手に作物の種を蒔いたり、苗を植えたりしてしまうことをいう。もし訴訟相手からこれを強行された場合、された側は「種蒔きや田植えの手間がはぶけた」などといって呑気に笑っていてはいけない。すぐにその土地に駆けつけて田畑を「鋤き返し」(耕しなおし)てしまわなければならないのである。なぜなら、それを放置すれば相手の用益事実を認めたことになってしまい、中世社会の場合、それは即、相手の排他的支配を認めたことになってしまうからである。
- 前の記事
- 内部の人間の犯罪 秋山駿評論集
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
いちえふ 福島第一原子力発電所労働記(1)~(3)
2018/10/21 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co
山本夏彦の言う「戦前戦中 まっ暗史観」を思い出した。どんな過酷な状況だろうと、人 ...
子どものトラウマ
2014/07/04 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co
これまたいい本。子供に関する本はいろいろ読んでいるが、実に興味深い対象である、と ...






