メディアと芸術 ―デジタル化社会はアートをどう捉えるか (三井秀樹/集英社)
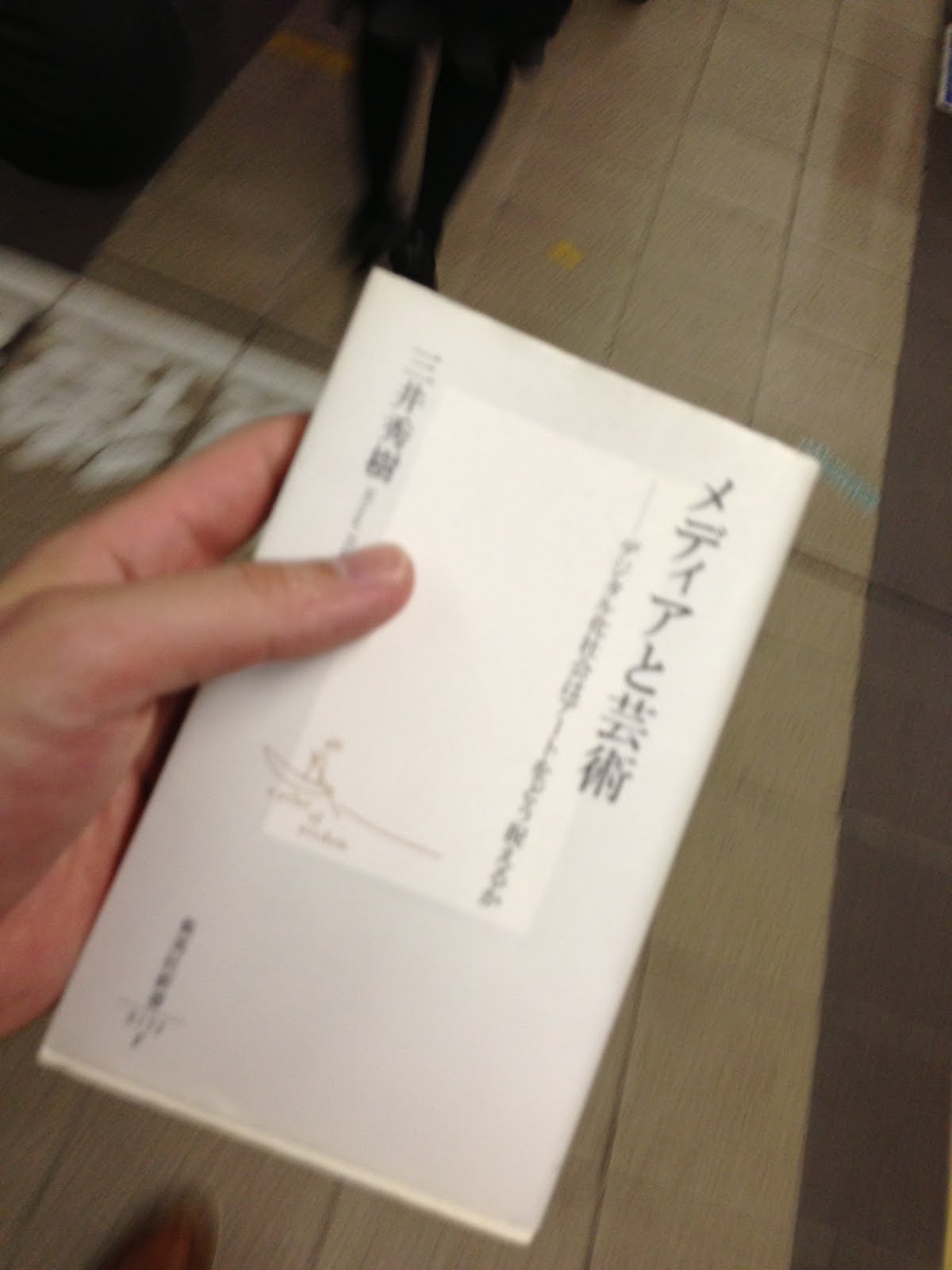
購入価格:251円
評価:
この記事は約2分43秒で読めます
いい本だといえばそうなのかもしれないが、メディアと芸術というよりも、「メディアと芸術のあり方」というような内容である。
著者は美術系大学でデザイン関連の教鞭をふるう教授らしいのだが、まあそのせいだろう、いかんせん「ザ・教育:IT化社会の現代において美術教育とはかくあるべき」という感じの主張が強めである。
たとえば著者は、まずはコンピューターを通してではなく、絵の具や粘土といった生の手仕事を通して学ぶべきだと言っている。ディスプレイ上の無機質な実感のない世界ではなく、五感をフルに使って色や形に触れる。その後にはじめて、デジタル技術との融合、行き来をはかっていくべきだと。
言っていることはわからなくはない。むしろよくわかる。乱暴に言えば「人間なんじゃけえ家ん中でゲームやらパソコンやらピコピコばっかりせんと外で遊んで来いや」というようなことであろう。
ぼくなんかは、そんなこと当たり前ではないかと思ってしまうのだが、あるいは生まれた時からコンピューターに囲まれ、それが当たり前として育ってきた子供たちにとっては、そんなことを"わざわざ"言ってあげないといけないものなのかもしれない。と言ってもこの本自体10年前に出版されたものであるので、いまはもっともっと言わなければならないのかもしれない。
以下、内容の一部をご紹介。
1885年にコダック社が開発したロール・フィルムと、1889年にエジソンが発明したキネトスコープが、1895年のリュミエール兄弟による映画の誕生の契機となった。「工場の出口」と「ラ・シオタ駅の列車到着」は日常、人間が視る光景を初めて写真映像として捉えた映画表現であった。列車がホームに近づく映像が突然スクリーンに映し出されると、観客は慌てて席を立つほど驚いたと言われる。
ポロックは、この技法(アクション・ペインティング)によってたちまちニューヨークの寵児となり、それまでパリ中心の絵画市場をニューヨークに移す立役者になった、といわれている。
デザインとは、車や家具、ポスターのように用をもった、つまり使用目的に合わせた機能をもった美術である。
以上。
ポップアートが流行した1960年代。パリからニューヨークへとアートの中心が移る、その変化。なるほど、ポロックの存在が大きかったのか。アメリカのスーパースターと言われるだけのことはある。
- 前の記事
- 名著12篇に学ぶ中国古典の人間学
- 次の記事
- 日本の現代アートをみる
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。