ひとつの日本文化論 (寺井美奈子/講談社)
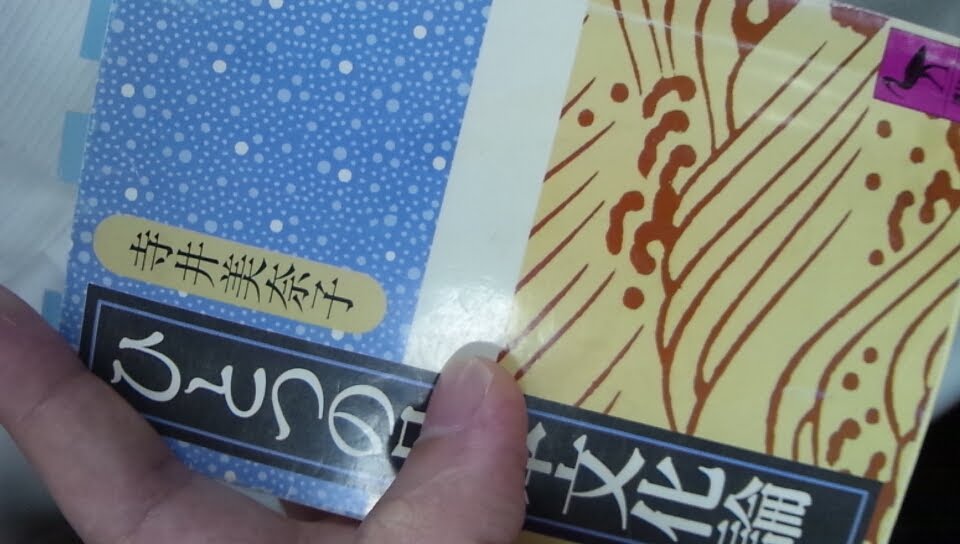
購入価格: 不明
評価:
この記事は約2分58秒で読めます
おもに着物という日本の文化を足掛かりに論が展開されており、着物になる前の布を織ることの意味、紐で結ぶという着方に込められた意味など、ひとつひとつに深い思想があることを教えてくれる本。
のだが、いかんせんこの著者が嫌味っぽくていけない。基本的に最近の若者はけしからん、最近の日本は堕落してしまっておる、というようなスタンスがいちいち透けて見える。
嫌味など出さずもう少し素直に書けば、豊富な知識・見識で万人の教養に役立つ本になったろうに、なんて、いまでは十分に老婆だろう著者に余計な老婆心を抱いてしまう程度に残念。出版は昭和54年で1937年生まれの著者である。
以下、興味深かった箇所をご紹介。
・衣服の起源としては、性器の保護がある。身体の中でこの部分だけは特に柔らかく、昆虫類などに襲われる恐れがある。蛇が男の化身として女のもとに訪れ、子を孕ませるという伝説が三輪伝説などに残っているが、これは男の性器を蛇にシンボライズさせたもの以前に、女の性器が蛇に狙われやすかったことからきたものであろう。
・稲が渡来してからは、気候に支配される自然の中で秋にたくさんの収穫をあげるために、いよいよ人間わざ以外の神の力にたよらざるをえなくなり、本格的な信仰へと入っていく。いったいに宗教がおこるのは、不安が生じてきたときであろう。その日暮らしに徹していられる人間にとっては、宗教というのはあまり関係がない。それゆえ農耕民族の場合、人間が生きていくうえにもっとも大切な食物に天候がかかわってきたときを本格的な宗教のはじめと見る。
・古事記に、スサノオという神様が、女たちが機を織っている忌服屋(いみはたや)に皮を剥いだ馬を投げ込むという暴挙に出て、ひとりの服織女(はたおりめ)がおどろいて梭(ひ:機のヨコ糸を通す時の道具)で陰(ほと)をついて死ぬという話がある。これは昔、女性の経血で染色をしていた証拠である。また、沖縄の竹富島に、経血で染色をしていた例が残っており、明治のはじめまで行われていたという。
特にこの三つ目の話は、点と点がピーンとつながった感じでひとりで納得しまくってしまった。というのも今年読んだ本の27冊目で【楽しい古事記】阿刀田高/角川文庫の中で、このスサノオの話を読んだのだが、確かにいくら驚いたからといって「陰=性器」をついて死ぬというのは不自然すぎる。となると、そのとき、何らかの理由で性器に触れていたと考えるほうが自然だろう。経血で染色作業をしていたとなれば、確かに驚いてブスッとなるのもうなづける。
とりあえずこの三つ目の話だけで、ぼくにとっては十分この本を読む価値があった。
- 前の記事
- 強権と不安の超大国・ロシア 旧ソ連諸国から見た「光と影」
- 次の記事
- 動物農場
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
基本ルールで話せる・書ける 英文法ポケットガイド
2019/05/17 エッセイ book, english, migrated-from-shintaku.co
淡々と英語学習を続けている。なんか英語の勉強も一周した感があるので、今後は乱読は ...
ネイティブスピーカーの英文法―英語の感覚が身につく
2017/04/02 エッセイ book, english, migrated-from-shintaku.co
やっと英語の知識が中学生くらいになってきたなあと思う今日この頃。










