「世間」とは何か (講談社現代新書): 阿部 謹也: 本
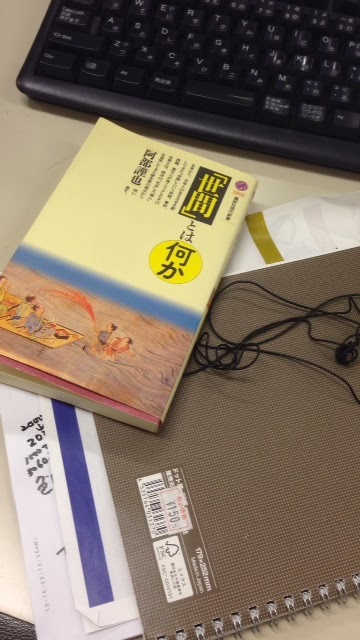
この記事は約3分13秒で読めます
多くの人にとって、写真と言えば友人や家族を写したポートレートであろう。つまり日常生活の一部としての写真である。
しかし写真史という一つの歴史として見ると、むしろ非日常的でダイナミックな時代のうねりが浮かび上がってくる。
写真とは何か
絵画や彫刻に比べれば、圧倒的に写真は新しいメディアである。
私たちが使っている「写真」という言葉の起源を遡ると、古代中国の文献に行き当たる。紀元五世紀の南朝宋時代に成立した『世説新語』や、六世紀の六朝末に成立した『顔氏家訓』という書物にその用例が見られ、人物をありのままに写生した肖像画として使われている。その後、日本に伝わった「写真」は、貴人の肖像や神仏を描いた画を指す言葉となった。この意味が変わり始めるのは一八世紀半ば、江戸時代中期である。この頃から肖像画に限らず、リアルに対象物を描きだした絵画全般を「写真」と呼ぶようになった。
写真はまず、絵画の延長線上において理解された。かつては限られた権力者や素封家だけが自身の肖像画を持つことができたところに、写真術は風穴を開けたのである。
それを思えば、誰が写真をメモ代わりに使うような時代を想像できただろうか。
眼の延長としてのカメラ
芸術的な写真の良し悪しを理解するのは難しい。その理由のひとつは、絵画と違い、誰でもシャッターを押せば、リアルな画像、本物らしいビジョンを得られるからであろう。
森山の写真が私たちに物語るものは「見られるつらさ」ということである。熱海の観光地、見世物小屋の看板、名もないストリッパー、ドサまわり旅役者一座の「見られるつらさ」というものは、実は同時代の共通感覚であって、見るためには見られねばならないという社会生活の約束へ、いたわりと泥足でふみこんでゆくという感じがある。
写真は絵画のように単純に技術の巧拙を面白がってわかったような気にはさせてくれないのである。思うに、写真はそこに映し出されたものよりも、もっと、作家自身の態度にこそフォーカスして見るべきものではないだろうか。
写真を再定義する
絵画や彫刻は、ルネサンスを起点としても千年近い歴史があるために、それ自体の定義は一応固まっている。
一方の写真は、いまだ発展途上で、その定義自体が現在形で揺れ動いて定まっていない。
初期の森村に対しては写真買いから反発もあった。自分でシャッターを切らないものを写真作品として認めないという素朴な意見や、写真を単なるメディアとして使っているだけという批判である。
シャッターを切ることが写真には必須か否か――これは今でも再検討してみる価値がある切り口ではないだろうか。
杉本の作品が欧米で受け入れられたのは、時間や空間を超越してものの起源に迫るというそのコンセプトと、作品自体の工芸的ともいえる美しさにある。しかも、そこからは日本の伝統美術や禅の精神と近い印象を欧米の美術関係者に与えた。たとえば「ジオラマ」に見られる虚実が交錯するような面白さや「見立て」の感覚、あるいは「シアター」と「シースケープ」における大胆な余白からは「間」の美学といった、日本美術特有のキーワードを容易に連想させたのである。いわば新しいジャポニズムの再解釈という側面があった。
杉本博司の作品の何たるかを理解していなかった私にとって、この説明は素直に腑に落ちるものがあった。
最後に、志賀理江子の作品集『螺旋海岸 notebook』にある記述を引用しておきたい。
写真はそこに何が写っていようがいまいが、写真であるだけ拾われましたが、その価値は「ただ」の紙切れから「自分の娘そのもの」にまで激しく変化する。その振れ幅によって写真の価値のあり方を身を持って知らされた気がしました。 (中略) 写真に希望を託してよいのだと思います。たとえ写されたものが残酷ななにかだったとして、記録に幻滅して苦しさだけが残るだろうと思っても、期待してよいと思います。必ずそこには新しい感覚があるはずです。
東日本大震災に関するプロジェクトを通して語られた言葉だが、写真とは何かを考えるうえで、非常に重要な指摘だと思う。
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
日本人の9割が知らない英語の常識181
2019/01/27 エッセイ book, english, migrated-from-shintaku.co
肩肘張らなくていい新書は英語の勉強におすすめ。むろん読んだところで9割は即忘れる ...










