生活リズムの文化史 (加藤秀俊/講談社)
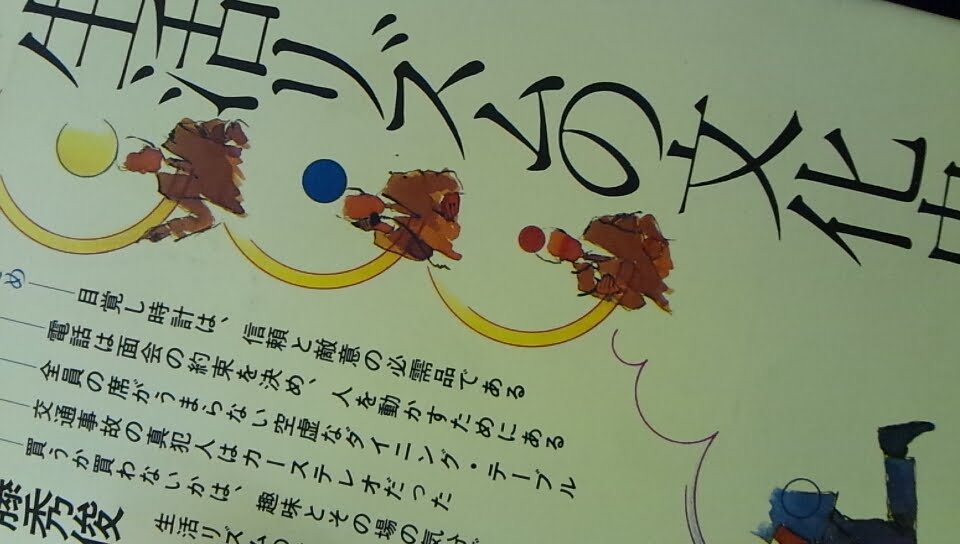
購入価格: 不明
評価:
この記事は約1分1秒で読めます
いかにも学者だなあという作者が、ぼやぼやととりとめもなく考えを綴ってみました、という感じのゆるい一冊。
どこか世間離れした――へえ、庶民はそんな感じで生きてるんだねえという距離感――ものごとへの眼差しが微笑ましい、というより、うらやましい。ぼくもそのようにぼんやり生きていきたい。
さて、断片的に内容紹介。
江戸時代の人々は寺の鐘の音で起きていた。おもしろいことに、記録によると、こうした江戸のお寺はその鐘によって起きる人々から目覚まし賃とでもいうべき料金を徴収していた。現在の金銭に換算すると一月に150円程度だった。
作者の、戦後間もない頃の通勤電車の回想。
電車は焼け残りのオンボロ車輛。運転本数も少なかったから、文字どおり車内はパンク寸前。ガラス窓が割れるなどというのはごく当たり前で、ときには人間の圧力でドアが外れたりしたこともあった。ガラス産業も壊滅状態にあったので、窓ガラスの入れ替えもできない。割れたあとはベニヤ板を打ち付け、おかげで車内は真っ暗。それに加えて、停電もしょっちゅう起きた。満員のうえに、電車が20分も30分も停止し続けていたのでな、もうどうにもならぬ。夏の暑い日には、失神する人なども現れた。
本のタイトルはあんまり関係なく、作者の気ままなエッセイとしてみれば、まあまあ読む価値はあるかもしれない。
- 前の記事
- 言霊 なぜ日本に本当の自由がないのか
- 次の記事
- 古事記 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
偏見の構造―日本人の人種観
2021/04/14 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co
アメリカの心理学者ゴードン・オルポートの定義によると、「偏見とは十分な根拠もなし ...



