「なぜ?」から始める現代アート (長谷川 祐子/NHK出版)
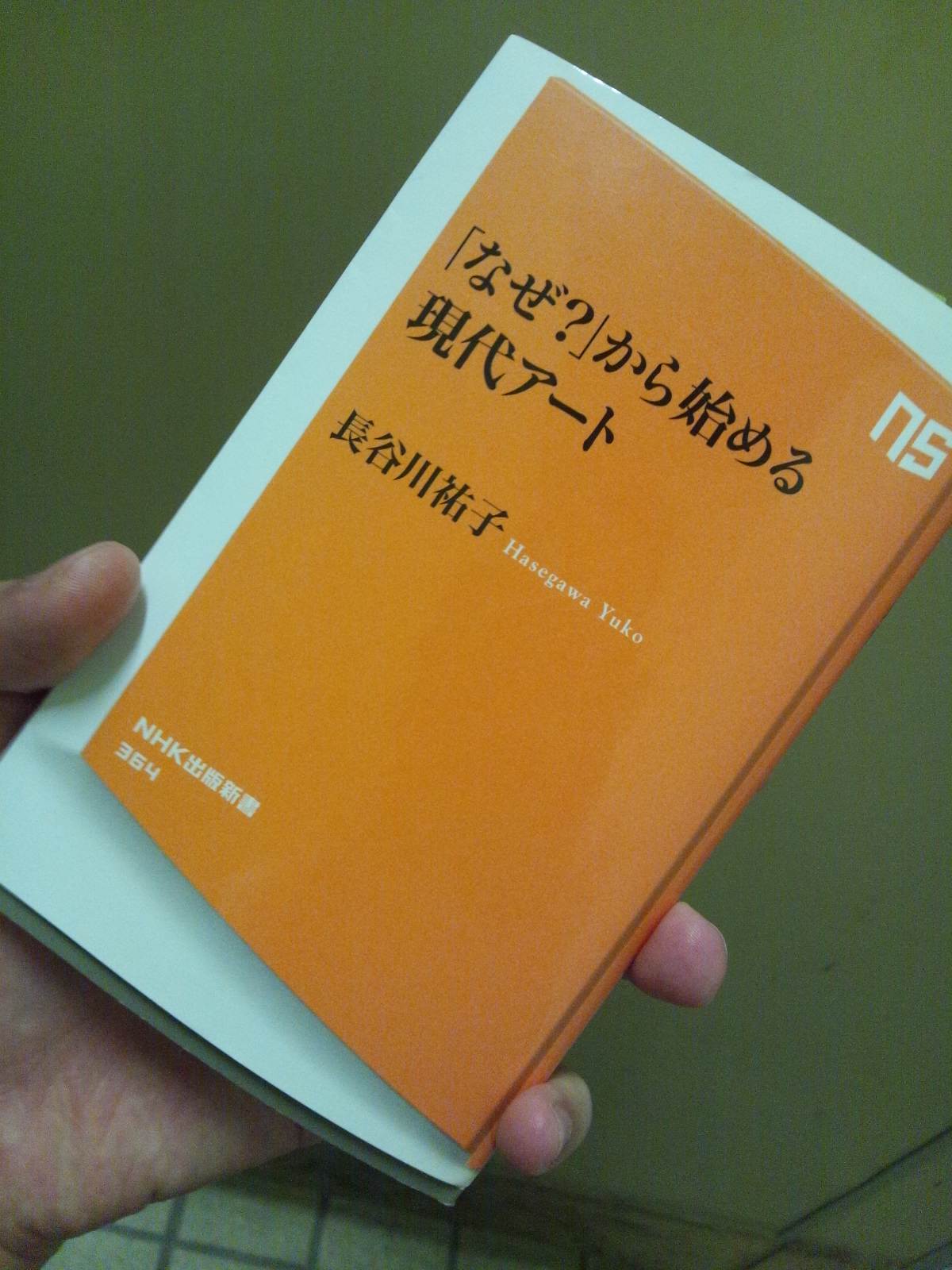
購入価格:609円
評価:
この記事は約3分30秒で読めます
著者は有名なキュレーターです。はい。金沢21世紀美術館の展示が話題になったりしたんですよね。はい。
はい。書籍のお金の出し惜しみをするのはやめよう!と思い立ち、Amazonで買いまくった本の中の一冊。最近の本が読みたい、そうだ、気が済むまでアート関連の本を読もうと、10冊くらいまとめ買いした中の一冊。
出し惜しみしないと言いつつ、実は買いまくった本はどれもお安めの本であるのはここだけの話でありご愛嬌である。
それはともかく、やはり最近の本はわかりやすいしおもしろい。こと、アートに関しては強固な興味があるからか、頭にすっと入ってくる。いつか興味が無くなる日がくるかもしれないので、今のうちに読み漁っておこうと思う。
現代アートって何?よくわかんないんだけど?という人のために書かれた本らしいが、実際、「現代アートって何?」って言ってる人にはどんな入門書もハードルが高いような気がする。
まあ、しかし一読すれば、現代アートというものがこの世にはあり、けっこう幅をきかせているらしい、ということくらいはわかるだろうと思われる。
以下、興味深かったところをピックアップ。
よく「書かれている歴史は強者の歴史である」といいます。〜中略〜アートについても同じことがいえます。美術史の本に載っているような作品というのは、明らかな意志の下に残されてきた。
アートを展示する白くてニュートラルな空間は「ホワイトキューブ」と呼ばれています。1929年に開館したMoMA(ニューヨーク近代美術館)から始まり、その後世界中に広がっていきました。〜中略〜初めてホワイトキューブに入った、あるイギリス人の言葉は印象的です。「月面に来たようだ」。それまでヴィクトリア朝風の装飾的な室内空間しか知らなかった人にとっては、何もない真っ白な空間というのは、まるで別の惑星に降り立ったような、それまでの空間認識がリセットされるような体験だったということです。
(ジェームズ・タレルの言葉)
「アーティストとは、答えを示すのではなく、問いを発する人である。」
(リクリット・ティラバーニャの作品について)
彼は1990年、NYのギャラリーで、パッタイ(タイ風焼きそば)をつくり、来場者にふるまいました。それは通常のギャラリーのオープニングのようで、みんなは楽しく食事をともにしました。その後、チリソースのこびりついた鍋や、エビのしっぽが残ったままの皿、観客が置いていったもろもろのモノもそのまま、会期中ずっと展示されたのです。〜中略〜彼はいいます。「もっとも美しい時間は、みんなと食事をしながら話す時間だ」と。〜中略〜一緒に食べたり演奏したり、そんな日常の行為をみんなと行うこと、その機会を無償で与えること(贈与)そのものを、彼はアートとしました。そんな大切なものを取り出してリ・フレームし、みんなと共有できるようにした。こういう作品について「日常行為をレディメイド化する」といういい方もあります。
以上
話は変わるが、あ、そうだ、美術検定を受けよう、と思っていたのに調べたらすでに終わっていたという話。まあまた来年、広島で受けるとしましょうか。来年の今頃は、オバマではないが、ぼくの人生が大きくchangeしてるんだな。きっと。つーかしてなきゃ困るんだけど!
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
マッカーサーが来た日―8月15日からの20日間
2021/10/05 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co
当たり前だが、終戦記念日は8月15日というたった一日しかない。しかし、そのように ...
英語プレゼンの極意: バーゼルで5000人の外国人をとりこにした奇跡のプレゼン
2017/11/26 エッセイ book, english, migrated-from-shintaku.co
極意ってほどでもないし、そんなん知ってるわということの方が多かった印象。










