観光アート (山口裕美/光文社)
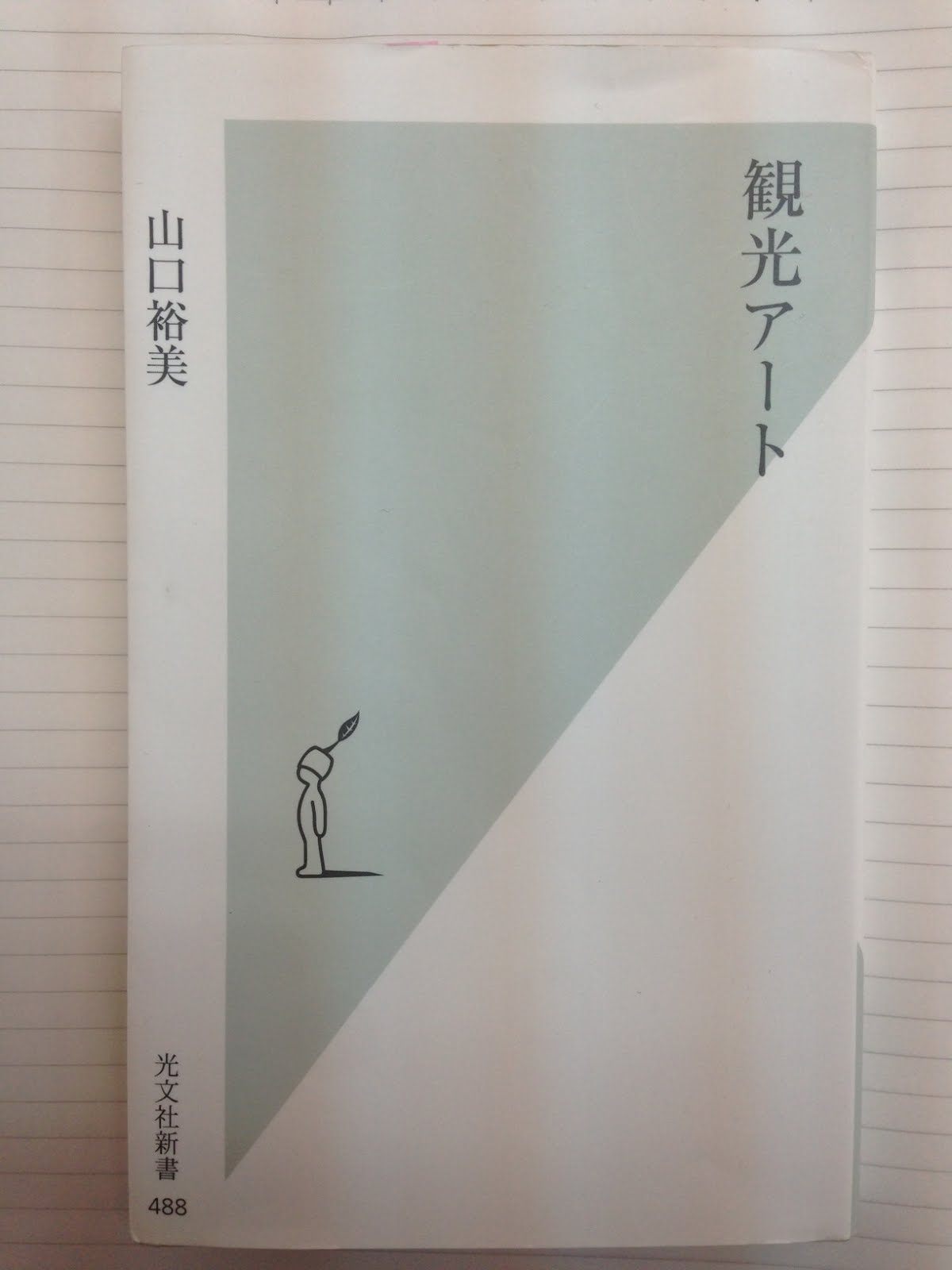
購入価格:463円
評価:
この記事は約2分1秒で読めます
内容=著者の個人的な熱い主張5割、全国美術館ガイド5割。
そういう本である。観光アートと銘打っているので、何やら新しい概念かと思ったが、要は最近ことに活発になってきた地方発のビエンナーレトリエンナーレは一見の価値あり。地方の美術館で異例の観客動員数を叩きだす美術館も増えている。時間とお金をかけて行く価値あり。これで地域活性、町おこし、アートの力ここにあり、というような内容である。
具体的な成功例として、香川県の直島、「大地の盛り芸術祭」越後妻有アートトリエンナーレ、美術館では金沢21世紀美術館など。地方ならではの自然とアートが一体となって、五感をフルに使って楽しめる、とのこと。
著者いわく、成功の要諦は、地域住民を取り込むこと。最初は「アートなんてよくわからんもんはいらん」という感じで否定的だった住民を根気よく説得することで、いまではすっかり協力者になってくれているという。
予算はなくともおもしろいことができます、地域の既存インフラを活かして、地域の特色を活かして、もっと、アートで、活性化! ということである。
なんか解説が繰り返しになってきたので、もうとにかくは本文より興味深かった箇所を以下抜粋。
【「Cool Japan」という言葉は、2002年にアメリカの外交誌「フォーリン・ポリシー」誌に掲載された論文で、ダグラス・マッグレイというジャーナリストが初めて使った~中略~彼はGNP(Gross National Product)になぞらえて、GNC(Gross National Cool)、つまり「国民総クール指数」という言葉を作り~中略~】
(全国の美術館に対しての著者の主張)
【美術館は寄贈に対してもっと慎重になるべきだ、ということ。
ほとんど世間に知られていない地元作家が、膨大な数の作品を寄贈しているケースがそこかしこにあった。美術館の方には申し訳ないが、作品はきちんと吟味して購入を行うべきである。寄贈という言葉に甘えて、所蔵庫がそうした作品でいっぱいになるのは納得がいかない。】
引用終わり。
著者の寄贈についての主張は納得である。それこそ日本人的発想で「どうも寄贈なんてしてくださってありがとうございます」とただただお礼を述べるばかりになっちゃいがちなんだけれども、そこは、うちのコレクションの方針とは違うので等、お茶を濁してでも断る勇気が必要なのだろう。美術館の役目として「価値あるものを後世に残す」ということがあるが、価値がないものは残さない、という割り切った態度もまた重要だろう。それに、所蔵庫に眠らせておくのも決してタダではない。その分、新進の価値ある若手作家の所蔵スペースが圧迫されている可能性だって十分にあり得るのだから。
- 前の記事
- 絵巻物に見る日本庶民生活誌
- 次の記事
- 逆引きでわかる色鉛筆の技法書
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。
関連記事
子を授かろう(子どもは作るものではなく授かるもの)
2016/05/17 エッセイ, 家族・友人・人間関係, 社会・時事問題
かつて、子は〈作るもの〉ではなく〈授かりもの〉であった。受胎は人知の及ばぬことで ...










