DtoC After 2020 日本ブランドの未来 (株式会社フラクタ/宣伝会議)
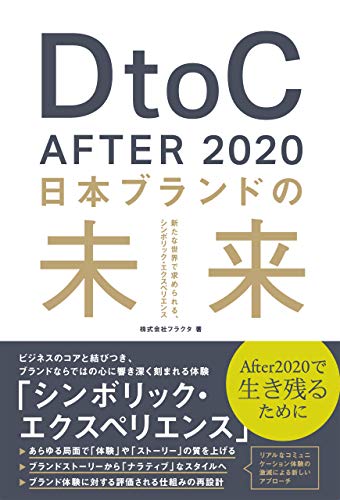
購入価格: Kindle Unlimited(0円)
評価:
この記事は約1分24秒で読めます
大量生産、大量販売、大量消費の時代の終焉し、個々人が網の目のようにつながって商売が成り立つ時代が見える。それは昔の小さな町の組合のような、濃厚な人間関係における口利きのような、古くて新しいカタチのように思われる。
消費者から見て、機能的な差異はアピールに乏しく、わざわざ新商品に飛びつく気になれない、という現象が起きていたと思われます。競合商品とのスペックの違いを訴えなくとも、DtoCは顧客を獲得し、維持できている。ここに大きく貢献しているもののひとつは、顧客との直接的、双方向的なコミュニケーションです。
アメリカでなぜDtoCが流行ったかというと、安くてよいものがあるからなんです。アメリカは貧富の差が激しくなって、消費者が同じ商品をもう買えないのです。なので、同じようなものなら値段が安いほうを買いたいけれど、ブランドがないとそれはそれで恥ずかしい。そういう意味で、ブランドの存在価値はありますね。だからどちらかというとDtoCは、今までのものを買えなくなった消費者に、よりよいブランドでよりよい価値、価格に見合うものを提供しているというのが、DtoC本来の考え方だと思いますよ。
マーケティングの初心者の方は、売りたい商品を買ってくれる人を探しています。つまり、誰に売るのか、ターゲットを決めない。大手のメーカーでも、「ターゲットはどういう方ですか」と伺うと、「買ってほしい人」ではなく、「買ってくれそうな人」をターゲットにしているケースが多いんですね。買ってほしい人をターゲットにすべきです。買ってくれそうな人に手当たり次第声をかけて、ではない。誰なら幸せにできるのかに向き合って、その人が喜んで買ってくれるまで何をしたらいいのか、を考えるのが最善だと思います。だから、マーケティングを始めるときは、ターゲティングをすることからやるべきだと思います。
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。



