カツ丼を喰らふ
最終更新: 2016/04/17
昨夜のこと。土砂降りで、風も強かった。ぼくは、お腹がすいていた。
家に帰るまでに、心がくじけそうであった。何がどうくじけるのかと言われても困るが、まあ、あれだ、くじけそうだったのだ、いろいろと。そんなわけで、とんかつでも食べて帰ろうか。そう思った。
代々木駅前に、前から気になっているとんかつ屋があった。そこに行ってみることにした。雨脚に足元を濡らされながら、目当てのお店に到着する。傘を畳んで、入店する。なかなか清潔な店内である。うむ、嫌いじゃない。
ぼくはメニューを広げた。かつ定食とかつ丼がメインのようである。まあ、とんかつ屋なのだから当り前といえばあたり前である。ぼくはなんにつけても定食という形式が好きなので、ロースカツ定食にしようかと思った。が、しかし、たまには王道のカツ丼にしてみようかなという気にさせられた。なぜなら、グレードとして「梅・竹・松」とあったからだ。実に本格的である。うむ、悪くない。
ぼくは給仕を呼んだ。「カツ丼の梅」と、注文した。10分足らずで、カツ丼(梅)は来た。ごく普通の、それこそ食品サンプルのように典型的なカツ丼であった。どこからどう見てもカツ丼である。丼の底からでも見ない限りは、「これは何でしょうか?」とクイズに出されたら、「こ…」で正答を出せるほどのカツ丼である。あるいは、これを親子丼という人が居たとしたら、君の家ではカツ丼を親子丼と呼んでいたんだねと憐れんでしまうほどカツ丼であった。
ぼくはおもむろに割り箸を取って、箸袋から取り出し、割った。左手に持った方が、やけに情けない感じで細く割れてしまう。どうやら心が乱れているらしい。のちにそれは、ぼくの無意識レベルでの動揺だったのだと知ることになる。
小判型のカツ丼の端っこに、箸を差し入れる。丼物を食べるときに、中心部から箸を入れるなんて無粋なことをする輩を、ぼくは心底軽蔑する。そういう輩には、ぼくはこう言ってやりたい。「おまえ、モテないだろう?」と。
たとえるなら、初めてのデートの待ち合わせにおいて、「待った?」と言うべきところを「ホテル行こうか?」というようなものである。馬鹿も休み休み言っていただきたい。
そういうわけで、ぼくは、ごく優しく、かつ爽やかに、「待った?」と言って、箸を入れる。そっと、持ち上げる。驚くべき肉厚のカツが、その肢体を露わにする。「マジかよ…」思わず声が漏れる。それは、押して引いての駆け引きのすえ、ようやくでデートにこぎつけた、死ぬほど魅力的なあの子のようであった。彼女は、「ううん。全然」と言って、ぼくの口へと導かれてゆく。いや、全然わいせつな意味じゃなくて。
口中に、出汁の味が広がる。それを追いかけるように、卵の甘味が舌の上で踊る。そこのところへ、じゅわっと、肉汁が染み出て、口腔内をぬるぬるぬめぬめとかき回す。いや、わいせつ表現ではなくて。
噛むごとに、モグモグのごとき効果音として「カツどん!」という音が立つようである。噛めば噛むほど、「カツどん!カツどん!カツどんどん!カツどん!カツどん!カツどんどん!」。
口の中でカツどんの音が小さくなり、やがて消え入ると、ぼくの食道を通って、胃袋へと落ちてゆく。腹の底で、ぼくは深々と納得する。了解する。あるいは悟る。(本当に、本当に、カツ丼でした)。
それは快感であった。いや、もう少し普遍的な、快楽であった。ぼくは、初めての自慰行為のような甘いめまいを感じながら、矢継ぎ早に箸を進めた。
ぜいたくな肉厚の豚肉を、あごを大きくストロークさせて、噛む。噛む。噛みしめる。これはいったい、なんという豚なのだろうか。はっきりとはわからないが、これだけはわかる。緑豊かな、広大な大地でのびのびと育てられた、限りなく天然に近い豚だといういうことだけは、はっきりとわかる。
なぜなら、この豚肉は、あまりにも素直なのだ。英語でいえば、honesty。自然、Billy Joelの名曲も思い出す。オ~ネスティ~……♪ それはともかく、素直。そう、素直な豚肉。噛もうと思えばいつまでも噛めて味わい深く弾力を失わず、噛み切ろうと思えば、まるで切り取り線があるかのようにすっと噛み切れる。これほど素晴らしい豚肉は、一般的な狭い豚小屋での劣悪な飼育方法では、到底実現不可能であろう。
ぼくは、我を忘れて貪り続けた。カツどん!カツどん!カツどんどん! そうして、はっと気が付く。我に返る。残るはカツの一切れと、一口分の、出汁に濡れた白飯であった。
その事実に、不意につむじ風が立つように、なんとはないさびしさと、しみじみとした名残り惜しさがこみ上げてきた。夏休みの最後の日のような、クリスマスの日の朝ではなく、プレゼントの興奮が静まりつつあるその夜のような、次の誕生日は一年後、つまり誕生日の次の日のような、近所のしめ縄や門松が消え、お正月の雰囲気が消えてゆくような。
しかし、それでも、先へと、未来へと進んで行かねばならない。絶対的な時間に支配された人の一生は、不可逆性の中でしか存在しえないのだ。あるのはただ、次の瞬間には過去になってしまうこの刹那と、恐ろしい勢いで迫りくる未来しかないのだ。
ぼくは、最後の一切れに、壊れもののように、そうっと、箸を添える。丼の底に点在する白飯を、一粒、一粒、思い出をなぞるように、丁寧に、愛おしく思いながらかき集める。そうして、カツと白飯を、ひとつの塊にする。カツと白飯は、形は整ってもいないし、むしろいびつとさえも言えたが、それが逆に、美しかった。泣き笑いの苦楽をともにして、ようやくで静かな晩年を迎えた、長年連れ添った老夫婦のような、美しさ。
ぼくは、美しい塊を、ゆっくりと、箸でつまんだ。いや、つまんだというより、ただ、添えた。そのまま、おそるおそる、持ち上げた。今にも崩れそうな、カツと、白飯の、塊。しかし、もろく、はかないからこそ、美しいのである。
ぼくは、あんぐりと、口をひらいた。舌の上にのせて、口をとじた。大事なものを、宝箱にしまっておくように。あるいは、絵本の中に見るような美しい女王様が、幽閉されるように。つまり、自分だけのものにするように。
ぼくは、悦びを、独り占めにした。誰にも渡さないし、邪魔させもしない、暴力的な幸福を味わった。ひと噛みごとに、カツ丼と、ぼくの全感性が、閃くように交感する。そこに生じるのは、藝術、あるいはアート。いやいや、そんな言葉で表現しようとする心がすでに卑しく、浅ましい。言葉はいらない。ぼくが存在する。カツ丼が存在する。その二つの存在が、出会った。ただそれだけなんだ。
ごちそうさまでした――ぼくは、店主でも、畜産農家でもなく、天にそうかしこみかしこみ申し上げた。熱いお茶をすすり、一息ついてから、店を出た。恐るべき、隠れた名店であった。数歩すすんで、思わず店を、振り返った。
極上のカツ丼を出す名店中の名店が、そこにあった。その名も、とんかつ・かつ丼「かつや」。全国チェーン展開中である。

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。
- 前の記事
- 2015/07/03 更新 わたしを拘束する機械
- 次の記事
- 2015/07/03 更新 たゆたう気力
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。







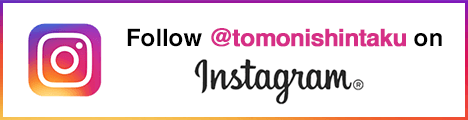

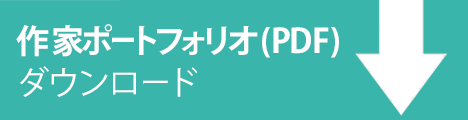

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。
わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!