居酒屋という異次元(後編)
最終更新: 2020/06/26
店内に先客は三人いた。ともに、あまり経済状況がよろしくないのだろう身なりで、50がらみと思われた。最近行った釣りでの釣果だとか、その時に雷が鳴って慌てて車に戻った、雷の時は車内が一番安全なんだとかなんとかいう、ほんとうにどうでもいい話を、いかにも大ごとであるかのように話していた。
そんなこんなを観察したり思ったりしているうちに、店員がメニューとおしぼりを持ってやってくる。店員というか、女将と言ったほうがしっくりとくる、恰幅のよい女性である。二重か三重アゴくらいで、心なしかトドに似ており、むやみに愛嬌だけはある。また血糖値や血圧が不安な感じではあるが、まあ、どこにでもいるふつうのおばちゃんである。
夫婦でやっているらしく、一方の大将はカウンターの前にある厨房スペースに立ち、パリッとした白の調理服を着ている。それは白髪の丸刈りにヒゲ面という容貌とあいまって、あるいは割腹でもしようかという雰囲気であった。
ぼくは、飲み物のメニューに目を通し、そこからレディースビールを注文した。本当はグラスビール程度がいいのだが、無かったので中ジョッキよりも量が少ないものを選んだだけである。
ほどなくお通しの「ねぎとろ」とともにビールが運ばれてきた。お通しにねぎとろとはなかなか結構と、ぼくは感心する。ビールをグイとやってから、箸をつける。うまい。心の底から、むくむくっと「良い気分」という、喜怒哀楽にも近い、具体的な感情が湧き上がってくる。
おばちゃんは、「お料理はその辺に貼ってあるのや、今日のおすすめのボードを見てくださいね」と言って、下がっていった。と言っても、すぐそばの椅子に腰かけて新聞を広げただけである。それはともかく、ぼくの裸眼では何ひとつ見えなかったので、バッグからメガネを取り出してかける。相当に悩んだ末、野菜天ぷらの盛り合わせを注文した。
しばらくの間、グッピーだかなんだかの小魚を眺めながらビールを飲んだ。それから【本当の戦争の話をしよう (文春文庫) ティム・オブライエン(著) 村上 春樹 (訳)】の続きを読み始めた。
「死者の生命」という編であった。『9歳のころ、ぼくはクラスメイトだった一人の女の子と両思いだった。お互いに思いを打ち明けたわけではなかったが、以心伝心というか、お互いに確かにわかっていたのだ』というような筋書きで始まる。
と、おばちゃんがぼくのもとにやってきて、「ちょっとお騒がせしますよ」と言う。振り返ると、そこにはカラオケ機器が設置してあり、どうやら酔客が歌うようであった。そういえば入口に「cyber DAM」の看板があったが、そういうことかと合点がいった。
「あじさい橋を、入れてくださぁい」
入り口付近でくだをまいていたおっさんが、おばちゃんに注文する。先ほどから、聞くともなく聞いているところによると、昼間っから飲んでいるらしく、すでに相当に酔っ払っているらしい。
曲が始まり、おっさんが歌い始める。開始5秒で判明する、ひどい音痴であった。しかし、おばちゃんは女性ならではの優しさと思いやりでもって、合いの手などを入れてあげている。まったく、おばちゃんという存在はつくづく偉大だと思う。
それに後押しされて、酔客は実に気分良さそうに、いっそう声を張り上げる。どう考えても歌唱力的に無理だろう”こぶし”らしきものさえも利かせようとはりきる。いくつになっても、男なんて他愛のないものである。
途中、ぼくと同年代もしくは若干年下くらいの、キャップを後ろ前にかぶって、やたらに耳にピアスがついている若者が入ってきた。おっさんらとは顔馴染みらしく、軽口を交わして自然に溶け込む。
おっさんの一人は「お、今日はなんかいつもと違うね。デートか?」なんて声をかけ、若者は「いやいや、彼女なんてできてないですよ」というような調子である。
ぼくはそれらを耳にしながら、小説の文字を追う。『彼女はサンタクロースがするような帽子をかぶっていた。一日中、ずっと、それをはずさなかった。ある時、クラスの悪戯っ子が、彼女の帽子を無理やりにはぎ取った』。ぼくは段々と物語に引き込まれてゆく。
おっさんは立て続けに曲を入れた。すべて演歌で、しかし、すべて音痴だった。
隣では、若者とおっさんの会話がはずむ。「東村山はね、陸の孤島ですよ。東京はどこも人が多いと思ったら間違い。東村山は孤島」
おっさんの音痴な演歌は延々と続く。おばちゃんは呆れることもなく、要所要所で合いの手を入れてあげる。常人にはとても真似できないやさしさである。男は度胸、女は愛嬌とはよく言ったものである。
ぼくはこの状況に自然と口角を上げながらも、とにかくは文字を追うことをやめない。『その瞬間、彼女は短くキャっと叫んで、うずくまった。その頭は、完全な丸坊主ではなかったが、幾束かのブロンズの髪の束のすきまから、地肌が露わになっていた。ぼくはそれを止めるべきだとは思ったが、身体が動かなかった。』喉もとに涙っぽいものがせり上がってくるのを感じる。
目頭を熱くしながらも、耳は閉じるということを知らない。「そうだそうだ、あそこは東京じゃない。新宿とかなら出会いもあるだろうけど、東村山はなんの電車も通ってないんだから、ひどいもんだよ。あ、三宅島もか」
居酒屋の中におっさんの調子っぱずれの歌声が満ち満ちる。しかし、どうして、それは不快ではなかった。
『それからしばらくして、彼女は死んだ。父に連れられて、彼女とのお別れに行った。棺に収まった彼女の顔を見た時、冗談だと思った。風船みたいに膨れていて、全然彼女ではないと思った。別人だと思った。本当の彼女は、いまにもそのあたりから、笑いながら飛び出してくるような気がした。』ぼくはもう、ほとんど泣いていた。
それでも、おっさんと若者の他愛ないやり取りもしっかり聞こえている。「まあ、まだ若いんだ。じきにいい出会いがあるよ」「そうだといいんすけどねえ」
おっさんの演歌には、罪がなかった。もちろんずっと聞き続けていたいというような種類のものではなかったが、その時その場所で流れる音楽としては、それ以外にはあり得ないような気がした。
『ぼくは長い間、彼女ではないような彼女を見ていた。父さんがいった。もういいだろう、外でアイスクリームでも食おう。』ぼくはいよいよ涙をこらえ切れず、おしぼりをメガネの隙間から差し入れて、目じりを拭い、拭い、ラストへと読み進める。
取るに足りないおっさんと若者の会話は続く。酔いどれのぐだぐだの音痴な演歌も続く。ぼくの異様な幸福感の高まりと、感涙も続く。みな、それぞれ酔いが深まっていく。すべての人々の夜が更けていく。人生という有限の時間の中で、もっとも幸せな瞬間のひとつが駆け抜けてゆく。

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。
- 前の記事
- 2020/06/26 更新 居酒屋という異次元(前編)
- 次の記事
- 2016/04/08 更新 ある居酒屋に憤って気づくこと
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。







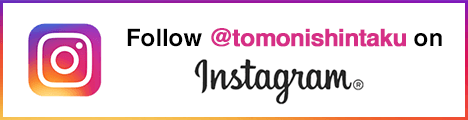

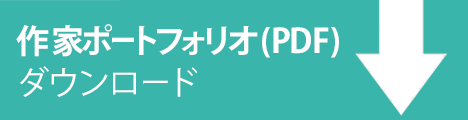

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。
わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!