(書きかけの小説)題名:わたしのための、わたしのための
最終更新: 2017/08/22
なにか小説を書きたいから小説を書こうと思う。と、こう書き出した時点で、いわゆる知識人は、ああメタ小説かと思うであろうし、たいていの人はメタ小説、はてな、となるであろう。
小説を書こう小説を書こうと思い立ってから、おおよそ十年が過ぎた。いや、正確には八年と十ヶ月。人間は、すぐに五年とか十年とか区切りをつけたがる。おそらく、人間の一生はあまりにも漠然としてつかみどころなく過ぎ去って、つまり死んでしまうので、ほとんど無理やりにでも区切りをつけ生を確かめようとするのだろう。なんて書くと、ちょっと小説らしい感じがする。というか自分がその気になる。こういう感じの描写を、要所要所に織り交ぜて、それっぽく書き進めていきたいと思う。
ああそうだ。ちなみにぼくは、小説の勉強はけっこうした。谷崎潤一郎の、文章の指南書として名高い文章読本とかも読んだ。ほかにも、たくさん読んだ。それで、自分では勉強したと思っている。だからまあ、ぼくの文章力は、ふつうの人よりは高いと考えてもらってかまわない、というか、この小説の終わりまでにはそれを証明したい。というか、あなたがこれを、紙媒体にしろweb媒体にしろ、一般的な商業流通を経て読んでいるのであれば、きっと何しかしらの形で証明されたということなので(絶対に自費出版なんかしないから)、ぜひとも期待して読み進めていただきたい。
それはともかく、人生にはきっかけというものがある。ぼくやきみが生まれたのだって、なにかきっかけがあったからで、いや、きっかけというか偶然というか単なる出来事または成り行き。なんでもいいが、ぼくが小説を書こうと思ったきっかけは、上京して数ヶ月のころ、ふと立ち寄った渋谷駅構内の書店で買った一冊の本だった。こういうのはあまりにもベタだが、しかし、およそ人の人生なんてベッタベタでできているに違いないから、別に恥じることではない。
それはドストエフスキーの地下室の手記という本だった。だが内容は、それほどよくは覚えていない。ただ、ラストあたりに出てくる言葉に、これもまたベタだが、がつーんと、頭をぶん殴られたような気持ちになった。ベッタベタを通り越してヌッルヌルだが、本当にそうだったのだから仕方がない。
『安っぽい幸福と高められた苦悩と、どちらがいいか? というわけだ。さあ、どちらがいい?』
突然こんな一文を出されても意味不明かもしれないので、そこに至る流れをもう少し引用して紹介しよう。
『世界が破滅するのと、このぼくが茶を飲めなくなるのと、どっちを取るかって? 聞かしてやろうか、世界なんか破滅したって、ぼくがいつも茶を飲めれば、それでいいのさ。』
これでもまだよくわからないという人には、原本を読んでくださいと言うしかない。まあ、極端な自意識過剰の果ての果てみたいなことなんだけど(ぼく自身忘れているのでウィキペディア参照)、重要なのはここ、「安っぽい幸福と高められた苦悩と、どちらがいいか?」というところ(このフレーズだけは覚えていて、忘れない)。
これを読んだとき、ぼくは思った。思ったというより、感じた。しびれた。うおお、なんてかっこいいんだと、打ちのめされた。それから小説家になろうと思うのに、一日とはかからなかった、という高校生、ではなくて大学生、でもなくて大学を留年しつつ卒業したばかりの23歳だった。いま思えばちょっと痛々しい。しかしまあ、それによってぼくは、「東京で小説家を夢見てがんばるフリーター」になった。「東京でぼんやり夢見てがんばるフリーター」よりは、たぶん、出世である。かっこよくいえば、ドストエフスキーがぼくの一生を変えたと。まあ、そんなことで人生が変われば苦労しないというのが現実の人生なのだが。
「安っぽい幸福と高められた苦悩と、どちらがいいか?」
はい高められた苦悩ですと即答するぼくは、しかし、行動力はそこそこあったので、すぐに小説を書き始めた。テレアポのバイトの昼休憩や、帰宅後に、紙で、パソコンで、思いのたけをつづった。
しかしこれが間違っていた。小説は思いのたけをつづるものではなかったのだ。小説は言うまでもなく物語をつくるものなのだ。だけどその時のぼくは、そのことに気づけなかった。だから、思いのたけを、ほとんど感情の掃き溜め的な、あるいは自伝的な小説を書きつらねた。しかしこの小説もまた、当時を多かれ少なかれなぞるので、結局ほとんど進歩していない気もするが、違うのは、メタのメタになるということ。そう、この小説はメタメタ小説なのだ。しかし、子供のころ、超スーパーとかいう単語に何の疑問も抱かなかったが、今ではちゃんと違和感を覚えられるようになったので、メタメタ小説という名称の違和感はちゃんと認識できている。だけど、それでも、メタメタ小説ということで、ひとつよろしくお願いしたい。
ぼくは若くて、小説家を目指す日々はきらきらしていた。決して誇張ではなくて、自己表現の喜びとやりがい。日に日に夢に近づいていっている実感。バイトで質の悪いお客に忙しいんだとどなられても、同じ拘束時間を似たような過ごし方をしながらバイトとは雲泥の差だった上司の給与を知っても、まったく平気だった。それはもう、不思議なくらい。小説の中に自分のすべてがあるのであって、バイトの中に自分はいなかった。かろうじてバイトに何がしかを見出すとすれば、自分の衣食住の保証くらいのものであって、いわゆるアイデンティティは、脳みそのしわ一筋もなかった。
小説家になるための王道、文学賞に応募したのは半年後くらいだった。しかしさらに半年後、あえなく落選した。落選の通知がきたわけではない。予選通過者は月刊の文芸雑誌にて公表されるのだが、ぼくの名前は公表されていなかった。何度も何度も確かめたが、ぼくの名前はなかった。いやもちろん、その文芸雑誌の中の文字を恣意的に拾い集めれば、きっと難なくぼくのフルネームを構成できるだろうけれど、それはちょっと、いやだいぶ違う。まあ、それくらい悲しかったということ。自尊心が、傷ついた。かなり。
だってぼくは、絶対に通過どころか受賞すると思っていた。若さって、怖い。いま思えば、ほとんど薬やってるのと変わりない。イっちゃってる。自意識の塊。そうだ、地下室の手記の主人公は自分に似ていたのだった。それから、自分という国の王様。王様一人に国民一人(一人二役)。しかしここは日本国。自分の国ではないから王様でもなんでもなくて、1億2000万人のなかの、居ても居なくてもどうでもいいような一人。いや、一粒。いや、ゴミ。ちりあくた。ああ、だめだ。ちょっとその時分を思い出して卑屈になってきた。世界は自分の思い通りに、ならない。自分はそれほど素晴らしく、ない。それってすごく、悲しいよね? って、同意を求めたがる若者みたいになっちゃったよ。あー、歳とったなと、しみじみ。今年で32歳のぼく。
若さとは、真剣だということである。いや、懸命と言ったほうが正しいかもしれない。ヤンキーだって、非行を懸命にやっている。片手間で非行をするような奴はまずいない。若者は、自己の存在が常に揺らいでいる。自分は何者かという問いに、どうにかこうにか答えを出し続ける。それはほとんど日毎にコロコロ変わるのだが、しかし、そのひとつひとつの答えを適当にではなく、本気で、大真面目に信じている。そして過剰に傾倒する。それはほとんど崇拝で、あるいは信仰にも似ている。しかしその時期を抜け出た者にとって、いわゆる大人から見れば、ひどく危うい。しかし同時に、羨ましく歯ぎしりするほどに、みずみずしくもある。
全身全霊で文学賞の受賞を信じ、見事に打ち砕かれたぼくは、きっと、みずみずしい憂いを帯びていたのだと思う。だからかどうか、彼女ができた。って、なんか小説の定番みたいな流れで三流感が尋常ではないが、いやもちろんこれは小説なんだけど、でも多分に現実も混ぜてるんだけど、ほんとにそういうものなんだよ、現実って。動物のように吠えて無差別殺傷したいくらい、ベタベタでヌルヌル。自分の人生は、自分の人生だけは特別だって誰だって思いたいものだけど、ぼくなんて人一倍自分を特別視していたけれど、全然特別なんかじゃなかった。ふつうの、凡人。がっかりするくらいに並のひと。しかしとにかくは彼女ができた。彼女って、誰だってできるもので、特別でもなんでもないこと。
話はちょっと脱線するけど、中高生くらいのころのぼくは、女の子によくこう言っていたものだ。彼氏の有無をたずね、いないと答えられると「え、彼氏いそうなのに」って。その頃のぼくは、恋人の有無をイコールでもてることだと思っていた節があって、それで、ぼくにとっては恋人がいそうだということは褒め言葉だったらしい。いま思えば、あきれるほどに意味がわからない。醜女でも醜男でも、世の中はうまくできているもので、つがう異性はいるもの。よく街中でいちゃついてる見苦しいカップルがいるが、タデ食う虫もってやつ。だから、もてるもてないは全然別の話。しかしなんだったんだろう、あのころのぼくは。まあ、たいていのことは若気のいたり、思春期ってことにしておけばだいたい間違いない。
なんの話だったっけ。ああ、彼女ができたって話。その彼女に、ぼくはけっこう愛された。たぶん、前出の若者特有の憂いが、女性にとってはちょっとかわいくて、特に年上の女性にはいっそうかわいらしくて、というか滑稽で、はからずも母性本能をくすぐっちゃったりしたんだろう、なんて、適当な分析だけどそれほど的外れではない気はしてる。
しかし愛されたと言っても、母の愛だとか、マザーテレサ的な慈愛だとかいうものではなく、しょせんは惚れた腫れたの類でしかない。つまり、どちらかの気持ちが大きくて、どちらかの気持ちが小さい。追いかけ、追われるという構図。それで、追われる側だったぼくはわかりやすく加速度的に傲慢になっていき、果ては自分をヒモにしてくれと、まるでちょっとコンビニへくらいの調子で言ってのけた。人って、というかぼくは、そういう性格なんだよ。純朴なふりをして自分の立場に異様に自覚的で、相手の気持ちを生かさず殺さず、隙あらば、どこまでも調子に乗って、利用する。それでも、彼女の答えは即答だった。いや、もしかすると、そう答えるしかなかったのかもしれない。
ぼくはめでたくヒモになった。だけど、ヒモになったと言っても、彼女はお金持ちでもなんでもなく、単なる派遣社員で、それほど稼ぎがいいわけでもなかった。しかもひとり暮らし。そうだな、たぶん手取りは20万ちょっとだったろう。給与明細を見せてもらったわけじゃないから知らないけど、たぶんそれくらい。そういう生活事情だったので、相談して彼女の部屋を引き払い、ぼくの部屋で同棲することになった。ぼくの部屋のほうが安くて広かったというのもあったけれど、それは建前で、ぼくは自分の居場所を失うリスクを巧妙に避けたのだと思う。何かあって関係が終わったとしても、出ていくのは彼女で、ぼくじゃない。そういう、こざかしい打算。それが男という生き物さ、なんて物言いはまたどこまでもずるくって、単なるぼくの性質だって正直に告白して懺悔したい。あくまでも形だけ、口先だけだけど。
ぼくの部屋はワンルームだった。でも、決して狭くはなかった。都内にしては十分に広かった。ベッドがひとつと、クローゼットがひとつ。ユニットバスでトイレと風呂は一緒くたで、キッチンは独り身にどんな食生活を期待しているのか無駄に広めだった。最寄駅の祖師谷駅からは徒歩20分と遠かったけど、ヒモのぼくにはもはや関係のないことで。まあ、箇条書くとそんな環境だった。
ヒモの生活は自堕落で単調だ。よく人はつまづくと、もう何もかもメチャクチャにしてしまいたいと口走るが、めちゃくちゃというのは、意外にこういう状態なのかもしれないと思う。めちゃくちゃって、すごく退屈。朝、仕事に向かう彼女を見送って、それからぼくは酒を飲む。杯を重ね、白昼を真っ黒に酔っ払って、文芸雑誌や小説をめくって文学そのものをこき下ろす。おれの文章のほうがよっぽど素晴らしいのになぜに世間は理解しないのだ、来たれ世界の終末。というのはつまらない冗談で、そこまで屈折もせず、けっこう規則正しく生活していた。
そういう性格だった。もちろんこの世にはそこでパチンコや酒や女や消費者金融等々に溺れる者もいるだろうけれど、ぼくはそういう性格ではなかった。それはぼくの優しさでも自戒でもなんでもなく、そもそもヒモなんてやってる時点でそんな自律的な人間の評価とは無縁だけれども、単にぼくの遺伝子のどこかに書き込まれている気質、性格、それだけのことに過ぎない。それでまあ、朝、仕事に向かう彼女を見送ると、すこしばかり散歩に出かけるのがぼくの日課だった。家から徒歩10分程度の祖師谷公園、ではなく、いつも間違えるのだが祖師谷公園ではなく砧公園だ。いや、やっぱりちょっと広めの公園、緑が多い整備された公園、という表現にしておこう。
この小説には、固有名詞は出てこない、というか出さない。使いたくない。それは単なるぼくの好みで、たとえば主人公の名前を森田にするとか、彼女の名前を理恵にするとか、そうしてしまうと、自ずと人物の印象が固定されてしまうことがどうにも気にいらないのだ。名称の響きのイメージの力というか、なんというか。場所にしても、東京タワーなどと限定すると、当たり前だがもうそれ以外のタワーではありえなくなる。
もちろん、小説の作法として、一般の人々の共通認識を利用するのは大事だし、感情移入を誘うのにも有効だし、それが大衆受けもしくは評価される小説の第一歩だってことは重々わかってる。でも、ぼくにはそれがどうにも我慢ならない。たぶん、いまだに小説をちょっと高尚なものだと思ってて、それで、どうにかこうにか、絵でいうところのモナリザのように普遍的なものにしたいという願望がある。だから、何か書きたい物語があるとか主張があるとかではなくて、ぼくは漠然と小説が、小説そのものが書きたいのだ。たぶん絵画であれば、ぼくはあくまでも絵画そのものが描きたいのであって、誰かとか何かを描きたいのではないから、たぶん、赤とか黒とかの純粋な色面を作ってよしとしただろう。
小説が書きたい。十年百年千年万年のあとも古びずあり続ける、小説としか表しようのない小説。小説としての小説。小説のための小説。そんな偉大な小説になる要素として、固有名詞を使わないことは全然関係がないし、むしろマイナスのほうが大きいこともわかってはいるんだけど、ぼくの感性がそれを許せないのだから仕方がない。ぼくはぼくとしたいし、彼女は彼女、公園は公園、タワーだって、タワーとしか書きたくない。そうすることによって、読者の頭の中に通天閣が浮かんだって、東京タワーがおっ立ったって構わない。
ふわり、ぼんやり、何を言っているのかよくわからないとしても、あいまいなままにしておきたい。もちろん、もっと掘り下げれば、それが大きな矛盾をはらんでいることもわかってる。どこまでが普遍かということだ。小説という概念や、ぼくや彼女という三人称、タワーという固有名詞はいつできたのか。たとえば46億年前の創世記にあったはずもなく、つまりぼくのいう普遍なんて、少なくとも人類始まって200万年とかそこらで、さらには文明が栄えて文字なるものが発明されて、文学というものが世間に浸透して……となると、たかだかここ100年200年くらいの話でしかないのではないか。まあ、ご都合主義にしろなんにしろ、それがぼくの芸術観。いささか安っぽいけれど、ぼくはぼくの考える普遍的で完全で完璧な小説を目指したい。個人的に、都合よく、そして適当に。
と、ここまで書いたところで、知り合いにメールで送って読んでもらった。この文章がいったいなんなのか、おもしろいのか否か、そもそも小説たりえているのか、自分ではよくわからないから。すると、良し悪し以前に、固有名詞を使わないとか宣言してるくせに「東京」とか「渋谷駅」とか思いっきり書いてあるじゃんって言われた。たちまち自分でも呆れた。さっそくの破綻。
まあ結局、ぼくの芸術観、というか小説家としての器なんてその程度なんだと思う。まったく、ぼくの目はとんだ節穴。おい自分。ここらでもう、諦めるか、認めるかしたらどうだ。文学賞など夢のまた夢で、落選は実に正しい結果だったのだ。ぼくという人間には、読者層を想定したり、物語の構成を考えたり、どのように人を惹きつけ、どうやったら人がおもしろいと思ってくれるか、評価してくれるか、そういう小説の基本のもろもろを作り上げる能力が全然足りないのだということを。とはいえ、仮に神様にそうはっきり言われたとしても、ぼくは小説を書くことをやめないだろう。誰だって、それくらいの譲れない自我ってあるものじゃないの。だから書く。とはいえさすがに初心は折れたので、固有名詞云々にこだわらず恣意的に書きなぐりたい。
さて、ヒモの生活は老人の生活にひどく似ている。彼女を見送ってから、コーヒーを飲んで、やおら立ち上がって散歩に出かける。片道10分あまりの道を、無目的にゆっくりと歩く。歩くために歩くという感じ。たしか初夏で、ぼくはサンダルだった。朝の通勤ラッシュは過ぎているが、それでも出勤途中とおぼしき人もちらほら散見される。あるいは営業の方々かもしれない。労働ご苦労さまです。あくまでも世間様にとっては忙しい朝なのである。
だからといってぼくは、別に優越感を覚えるわけでもなかった。それはいま考えるとちょっと不思議なくらいで、心持ちは変にニュートラルだった。世の正規雇用サラリーマン諸氏は一段下に見るのであろうが、バイトという非正規雇用労働者だったぼくだって、朝起きるのが辛い日もあったし、まったく行く気にならない日もあったし、実際行かない日もあった。そんな時は、誰かが変わりに働いてくれて、もしくは誰かが適当にお金をくれたなら、ぼくは一生自由で、のんべんだらりと気ままに寝起きできるのにと、迷走とも妄想ともつかないことを思い浮かべるものなのだ。
この世に人として生きている人で、そういうことを一度も思ったことがない人はたぶん人ではなくて、ブスかブサイク、というのは全然関係ないが、それはともかく、しかし実際その立場に自分がなってみると——もちろん最初の数日は喜びやテンションの高まりを覚えたが——それは普通の、日常以外のなにものでもなくなった。感動や感激は一瞬で、すぐあとには反動的な脱力にも似た冷静が待っている。慣れない刺激は無く、飽きない刺激も無い。
たぶん、究極的には、サラリーマンもヒモも、終わりなき繰り返される日常を生きねばならないという次元では、まったくもって変わりない。よって、どっちもどっちで、ただその身分の違いによってのみで幸不幸の判断はできない。うそだと思うなら、一回ヒモになってみればいい。そうすればきっとぼくの言っていることが真実だったのだと、軽い失意とともにわかるはずである。たとえばハワイに住みたいという人も、一回ハワイに住んでみればいい。この世に日常に堕ちない環境なんてありえない。ちなみにぼくはハワイに行ったことすらない。
公園に行っても、何をするわけでもない。小高い丘のようになっているところにぽつんと置いてある見晴らしのいいベンチに座って、公園全体を眺めるだけである。それに何を思うわけでもない。せいぜい天気がいいなあとか、まったく意味のないことを言語化されるかされないかという曖昧な次元で、ため息のように思うだけである。これといって見るべきものもない。そもそも雨の日以外は毎日来ているのだから、見慣れ切っている。そして平日の午前中なんて、母と幼児の組み合わせか、老人の散歩がせいぜいである。珍しいのはむしろぼくで、24歳の働くべきような若者が短パンTシャツといういかにも手に職のない浮き草のようなかっこうで、この時間にこんなところで何をやっているのかという感じである。
いや、目的はひとつだけあった。タバコを吸うのである。そのころ、2006年はまだ一箱270円だったと思うし、タバコに美学を感じていたりもした。非喫煙者になったのでよくは知らないが、今では一箱400円もするそうだし、嫌煙分煙かまびすしいこのご時世に、わざわざ喫煙所を目をさらのようして探しまわり苦労しいしいタバコを吸う人間なんて、ちょっとどうなの大丈夫と思ってしまう。かつての喫煙者の分際ではあるが、ついつい白眼視および嘲笑の鉄槌を歩きタバコその他にぶんぶん振り下ろしてしまう今日この頃である。まあ、ぼくは独断と偏見の塊なんだけど、でも、人間には少しくらいそういう偏りがあったほうが人間らしいし健康的でいいと思ってる、ってこれもまた独断と偏見。
つづく(時期は完全に未定)

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。
- 前の記事
- 2015/07/03 更新 ぼくという乗り物
- 次の記事
- 2017/08/22 更新 別に、どうでもいいでしょう
出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています
*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧
-
ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」
2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。
-
英語日記ブログ「Really Diary」
2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。
-
音声ブログ「まだ、死んでない。」
2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。







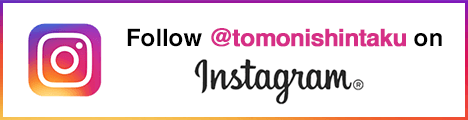

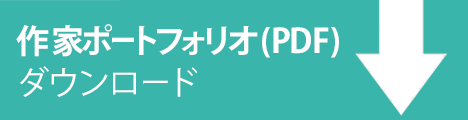

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。
わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!